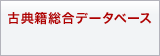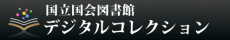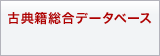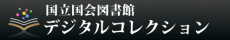『御伽艸子(御伽草子)』(おとぎぞうし)

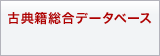
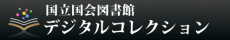
タイトル:『御伽艸子(御伽草子)』(おとぎぞうし)
編纂者:作者未詳
出版書写事項:明治廿四年四月五日(1891年)印刷
明治廿四年四月十日(1891年)発行
形態:二十三巻全二冊 和装(B6版)
校定者:今泉定介 東京小石川區西江戸川町一番地
同 :畠山健 同牛込區築土八幡町廿三番地
発行兼:吉川半七 同京橋區南傳馬町一丁目十二番地
印刷者
發賣人:林平次郎 同日本橋區箔屋町八番地
関西大:松村九兵衛 大坂市南區心斎橋南一丁目
販賣所
目録番号:win-0090003
『御伽艸子』の解説
『御伽艸子』(おとぎぞうし)は、江戸時代の享保から元文年間に活躍した大坂書肆の渋川清右衛門が、鎌倉時代から江戸時代にかけて語り継がれて来た物語の中から「いにしへのおもしろき草子」の23編を選び出して編纂し、『御伽艸子』または『御伽文庫』の表題をつけて刊行したものである。
渋川清右衛門は、大坂心斎橋順慶町に「柏原屋」の屋号で活動していた書肆で、古文辞学派の太宰春台(だざいしゅんだい・延宝八年・1680年~延享四年・1747)や、特に大坂出身の国学者である上田秋成(うえだあきなり・享保十九年・1734~文化六年・1809)の書籍を数多く出版している。奥付には「大坂心斎橋順慶町 書林 渋川清右衛門」の刊記があることから、「渋川版」とも呼ばれ親しまれた。『御伽艸子』の表題は「渋川版」の登録商標のようなもので、当初はこの23編のみを『御伽艸子』と言ったが、やがてこの23編に類する物語も指すようになった。
奈良時代に始まった「説話文学」や平安時代に始まった「物語文学」は、鎌倉時代には武家の台頭による貴族たちの衰微に伴い勢いを無くしていったが、それまでに無い新たな主題を取り上げた短編の絵入り物語が登場し、『艸子』や『草紙』や『草子』とも表記され庶民に流布した。『御伽艸子』は、四百編を超える物語が存在するといわれているが、室町時代を中心に栄えたことから、広義には室町時代を中心とした中世小説全般を指すこともあり、「室町物語」とも呼ばれた経緯がある。また、後に成立した「仮名草子」や「浮世草子」に比べて『御伽艸子』の全ては作者未詳である点が特徴でもあり、動物たちを擬人化させて、現代のアニメにも劣らないほどの空想力で構成されている。
現在では、「御伽艸子」「御伽草子」「御伽草紙」と言えば、この23編の物語草子を指し、草子物全体としては「お伽草子」「お伽草紙」と表記するのが通例となっている。この「御伽」については諸説あるが、漢字を「真名」(まな)と呼んだのに対して、平安時代から流行した平仮名を「伽名・仮名」(かな)と呼んだため、文学の世界では「かな書」の書物を総称した言葉であるとされている。この「御伽」とは、時代劇などに登場する「伽をつとめる」など、「話の相手となる」とか「寝室の相手をする」という意味で、私こと樹冠人としては、「子供などを寝かしつける為にする語り聞かせ」のことで、『御伽艸子』とは、丁寧語の「御(お)」を付けた「伽名を多用した読み聞かせ本」と解釈するのが適当であると思う。
今回紹介する書籍の校訂者である今泉定介(定助・いまいずみさだすけ・文久三年・1863~昭和十九年・1944)は、明治時代には国文学研究に励んだ古典学者であったが、大正時代には実践的神道論に影響を受け、「皇道」と呼ばれる思想を普及させた神道思想家であった。定介は昭和時代前半の国民に精神的影響を与えた一人で、彼の影響力は軍国時代当時の軍人・政治家・財界人にも及び「憂国慨世の神道思想家」と呼ばれた。しかし、戦時中の政府による海外神社政策や軍政策には断固反対を唱えたことは有名であった。日本大学構内に「皇道学院」を設立して社会教育の実践を続け、膨大な講義著作を生み出した。なお、現在では日本大学構内に「今泉研究所」が設置されている。
実は、現代までに「おとぎ話」が語り継がれている原因のひとつには、明治から大正にかけて活躍した児童文学作家で俳人でもあった巖谷小波(いわやさざなみ・明治三年・1870~昭和八年・1933)が貢献している。小波自身が編集した博文館発行の雑誌「少年世界」に「お伽噺」を再生して作品の多くを掲載した。以後同社の「幼年世界」「少女世界」「幼年画報」などの主筆となって作品を執筆し、さらに「日本昔噺」「日本お伽噺」「世界お伽噺」など、たくさんのシリーズを刊行した。今日有名となっている『桃太郎』や『花咲爺』などの民話や英雄譚の多くは彼の手によって再生され、幼い読者の手に届いたもので、日本近代児童文学の開拓者というにふさわしい業績といえる。その作品は膨大な数に上ったが、その代表的な作品が『小波お伽全集』にまとめられている。
今回紹介する書籍の目次には、「文正草紙・ 鉢かつぎ・小町草紙・御曹子島わたり・唐糸草子・小幡きつね・七草艸子・猿源氏草子・物艸太郎・さざれいし・蛤の草子・子敦盛・二十四孝・梵天國・のせざる草子・猫の草子・濱出草子・和泉式部・一寸法師・さかき・浦島太郎・酒顛童子・横笛草子」(目次表示に準ずる)の23編が順番に掲載されているが、参考までに概略を掲載しておく。
【文正草紙】
常陸国の鹿島大明神の大宮司に仕えていた文太は、ある日突然、大宮司に勘当され、その後、塩焼・塩売として財産をなして「文正」と名乗る長者となった。そして、鹿島大明神の加護で二人の美しい娘を授かり、ある日、姉は旅の商人と結ばれたが、その商人とは姉妹の美しさを伝え聞いた関白の息子である二位中将の変装であった。姉は中将に伴われて上洛するが、その評判を聞いた帝によって文正夫妻と妹が召し出され、妹は中宮となり、姉も夫の関白昇進で北政所となる。姉妹それぞれは子供に恵まれ、宰相に任ぜられた文正とその妻も長寿を全うしたという。
「文正草紙」(ぶんしょうぞうし)は、室町時代に成立したと考えられている物語のひとつで、塩売文正・塩焼文正・文太物語などの異名もある。常陸国(現在の茨城県あたり)は、かつては親王が国司を務める東海道の重要な拠点であった。主人公である文太が大宮司に勘当されたにも拘らず、立身出世して、娘たちも良縁に恵まれる話であるが、特に、「祝儀物」としてお正月の吉書題材や嫁入り道具の1つとして重宝された経緯があり、物語の内容を絵巻にした「文正草子絵巻」が室町時代以降から流布され、「文正草紙」は広く世間に知られていった。
【鉢かつぎ】
河内国の寝屋に、備中守藤原実高という長者が住んでいた。実高は長谷観音に祈願し、望み通りに娘が生まれ、やがて美しい娘に成長したが、母親が亡くなる直前、長谷観音のお告げに従い娘の頭に大きな鉢をかぶせたところ、鉢がどうしてもとれなくなった。母親の死後の鉢かづき姫は、継母にいじめられ家を追い出され、世を儚んで入水自殺をしようとしたが、鉢のおかげで溺れることなく浮き上がり、山蔭三位中将という公家に助けられ、風呂焚きとして働くことになる。その後、三位中将の四男である宰相殿御曹司に求婚されるが、宰相の母はみすぼらしい下女との結婚に反対し、宰相の兄たちの嫁との嫁くらべを行って断念させようとする。ところが、嫁くらべが翌日に迫った夜、鉢かづき姫の頭の鉢がはずれ、姫の美しい顔があらわになった。しかも、歌を詠むのも優れ学識も豊かで非の打ち所が無い様子であったので、嫁くらべの後、鉢かづき姫は宰相殿御曹司と結婚して三人の子どもに恵まれ、その後、若君の兄嫁たちと美貌や宝物や才覚を競う話がつづき、継母と不仲になって屋敷を出ていた父君との再会が果たされ、鉢かづき姫は、長谷観音に感謝しながら幸せな生活を過ごしたという。
「鉢かつぎ」は、「鉢かづき姫」「鉢かぶり姫」との異名もある。藤原実高が住んでいたのは、現在の大阪府寝屋川市の辺りとされ、寝屋川市の民話として現存している物語でもある。この姫は、初瀬山の長谷観音にちなんで付けられた「初瀬姫」と伝えられており、「かづき」は古語である「被く(かづく)」の活用形で「頭にかぶる」という意味となるので、現代語に訳して「鉢かぶり姫」とも表現されることもある。
【小町草紙】
和歌の才能で有名で天性の美貌を持つ小野小町が、老婆となり、見るも無残な姿で、都近くの草庵に雨露をしのいで暮らしていた。里へ物乞いに出ると、人々は「古の小町がなれる姿を見よや」とあざける。ついに、小町は東国から奥州へと流浪の旅を重ね、玉造の小野にたどりつき、草原の中で死ぬ。そして、在原業平が歌枕の跡を訪ねて玉造の小野まで来ると、吹く風とともに、「暮れごとに秋風吹けば朝な朝な」という歌の上の句が聞こえてくるのであった。
「清和のころ、内裏に小町といふいろごみの遊女あり。」で始まる「小町草紙」は、室町時代に成立したと考えられている物語のひとつで、「都近くの草庵」とは通称「小町寺」と呼ばれている隨心院と思われ、また、小野小町の奥州流浪死亡説の根拠となった説話でもある。近世になって渋川版御伽草子に収められ、濡れ衣を着せられた小野小町の悪評が普及した。
【御曹子島わたり】
藤原秀衡から「蝦夷の千島喜見城に鬼の大王がいて、大日の法という兵法書を所持している」と聞いた御曹子の源義経は、さっそく四国の土佐湊から喜見城の内裏へ向かい、途中、馬人の住む「王せん島」、裸の者ばかりの「裸島」、女ばかりが住む「女護の島」、背丈が扇ほどの者が住む「小さ子島」などをめぐった後に、「蝦夷が島」に至り、千島喜見城の内裏に赴いて大王に会う。兵法書を手に入れた後、四国の土佐湊に着いた。そして、奥州藤原家の藤原秀衡のもとに身を寄せたという。
源義経伝説の成立年代は未詳であるが、その伝説は日本全国津々浦々に存在する。「御曹子島わたり」は義経の奥州流浪に伴い奥州藤原家に身を寄せた時の逸話で、蝦夷の鬼退治伝説の根拠ともなった説話である。ちなみに、「大日の法」とは「法華経」を指している。
【唐糸草紙】
鎌倉御所に居た木曾義仲の臣下の手塚太郎光盛の娘である唐糸は、義仲に頼まれ源頼朝の命を狙うが、見破られて捕らえられ、松ヶ岡の尼寺に預けられる。しかし、尼公の計らいで信濃国へ逃れるが、武蔵国六所で梶原景時に再び捕らえられ、石牢に入れられる。その後、唐糸の娘である万寿は孝心厚く、鎌倉に赴き、鶴ヶ岡で十一人の手弱女(たおやめ)たちと伴に頼朝の面前で舞い、その徳により、めでたくも母を救いだすことができ、母や乳母の更科ともども本国に帰ることができたという。
平安時代末期に活躍した武将の手塚太郎光盛は、諏訪神社下社の祝部である金刺氏の一族で、源範頼・源義経の追討軍と戦い、最後まで木曾義仲に従った四騎の内の一人であった。
【木幡きつね】
山城国の木幡(こはた)に住む稲荷大明神の使者である狐の子供のなかに、貴種(きしゅ)御前という芸能優れた美しい末の姫がいた。十六歳の三月末のこと、三条大納言の子で、昔の光源氏か在原の中将かと見紛うほど容顔美麗な三位中将が花園に立ち出でたのを稲荷山から見下ろしていた時、恋の虜となり、人間の姿に化けて一夜の契りを結ぼうと、乳人の少納言と共に美しく化けて都に上った。その後、三位中将と偕老の契りを交わした貴種御前は翌年三月に若君をもうけ、大納言と北の方にも見参することができた。しかし、貴種御前は犬を飼わざるをえなくなり、古巣に帰り尼になったという。
表題の「木幡きつね」の「木幡」は、現在の京都の「木幡」のことで、この木幡地区では今でも「木幡きつね」の説話が言い伝えられている。また、「光源氏」は、あまりも有名な『源氏物語』の主人公であり、「在原中将」は、三十六歌仙で有名な在原業平のことである。また、『大鏡』『今昔物語集』『宇治拾遺物語』などに登場する狐の母から生まれた安倍晴明が、秘符と秘玉を与えられ陰陽師となり、蘆屋道満との腕比べで勝つ。この説話の狐の母「葛の葉」(くずのは)は、稲荷大明神こと宇迦之御魂神の第一神使であり安倍晴明の母であると伝わっている。このように、「きつね」との婚姻によって生まれた子供が特異な能力を発揮する説話は、『日本霊異記』などで見ることができる話で、古来より言い伝えられている話型である。また、この「葛の葉狐」は、信太妻・信田妻(しのだづま)とも変化して伝えられた経緯もある。
【七草艸子】
唐の楚国の「大しう」という者が、年老いた父母を見て嘆き悲しみ、山に入って21日間も明け暮れ祈願する。そうすると、帝釈天が天下り、「須弥山の南にすむ白鵞鳥が春の初めごとに七草を服すので八千年の寿命を保っている」と教える。そして、帝釈天は具体的に、「正月六日までに七種の草を集めておき、次の時刻に柳の木の器に載せて玉椿の枝で打ちなさい。」と。
酉の刻には芹(せり)
戌の刻には薺(なずな)
亥の刻には御形(ごぎょう)
子の刻には田平子(たびらこ)
丑の刻には仏座(ほとけのざ)
寅の刻には菘(すずな)
卯の刻には清白(すずしろ)
そして、辰の刻には七種の草を合わせ、東の方角から清水を汲み上げて煮て食べなさい。一口で十歳、七口で七十歳若返る。後々には、八千年まで寿命を得られるであろう。
早速、大しうは七草を父母に与え若返らせる。噂を聞いた帝は親孝行に感動して位を譲ったという。
「七草艸子」は、唐国から伝承された「七草摘み」の由来を説き、親孝行の功徳を勧める物語である。七草を酉の刻(午後五時から七時まで)から順番に準備して、不老不死の七草粥を食べる習慣は、現在では、一月七日に食べる慣習として全国に広まっているが、この「七草艸子」の影響が大きかったようである。
【猿源氏草子】
鰯売りの猿源氏が、和歌連歌の歌徳により、五条東洞院の「蛍火」との恋を遂げ、立身出世するというもので、猿源氏は光源氏の名を踏まえており、『源氏物語』の庶民版の草子物といえる。
【物艸太郎】
信濃国筑摩郡あたらしの郷に働かず寝てばかりの男がいた。村人からは「物艸太郎」(ものくさたろう)と呼ばれ、現地の地頭も呆れるほどの怠けぶりであった。ある時、都から夫役のお召しがあり、村人たちは皆嫌がっていたので物艸太郎をおだて上げて夫役に行かせることに成功した。上京した太郎はまるで人が変わったように働き者になったが、なかなか嫁が見つからない。そこで、人の勧めで清水寺の門前で「辻取」(路上で女を連れ去って妻とすること)を行う。たまたま通りかかった貴族の女官を見初め、妻に取ろうとするがその女房は嫌がり太郎に謎かけをして逃げ去ってしまう。ところが、太郎は謎かけを簡単に解いて、女房の奉公先である豊前守の邸へ押しかける。そこでは女房と恋歌の掛け合いをするが機知に富んだ太郎が女房を破り、ついに二人は結婚する。垢にまみれた物艸太郎を風呂に入れてやると見まごうばかりの美丈夫に変貌する。噂を聞きつけた帝と面会すると太郎が深草帝の後裔であることが明らかになり、甲斐と信濃の中将に任ぜられた太郎は子孫繁栄し、百二十歳の長寿を全うした。そして、死した後には、太郎は「おたがの大明神」、女房は「あさいの権現」として祭られ人々に篤く崇敬されたという。
「物艸太郎」は、「物草太郎」「物臭太郎」「ものぐさ太郎」とも表記され、室町時代に成立したと考えられている物語のひとつで、現代では「働かず寝てばかりの怠け男」の総称として使われることが多いが、実は、元来が高貴な出自の男性でないと呼称できない言葉である。「おたがの大明神」は長野県の「多賀大社」と「穂高神社」の説が存在している。そして、「あさいの権現」は「多賀大社」か「穂高神社」に隣接した「権現」であろうが所在不明である。
【さざれいし】
「さざれいし」の名称は、平安朝の姫君の名前で「さざれのきみ」という『御伽艸子』の中の主人公から全国に伝承されたという。さざれ石(細石)は、もともと小さな石の意味であるが、長い年月をかけて小石の欠片の隙間を炭酸カルシウムや水酸化鉄が埋めることによって、1つの大きな岩の塊に変化したものを指す。京都では下賀茂神社・北野天満宮など有名な神社には説明板と共に展示されていることが多い。
【蛤の草子】
天竺摩訶陀国の「しじら」は釣りをして母を養っていたが、ある日、美しい蛤を一つ釣りあげ、それは船の中で大きくなり二つに開いて、中から十七・八歳の容顔美麗な娘が現れる。四十歳になるまで女房を持たぬのも母へ孝養を尽くすためと言い訳する「しじら」を娘が説得して夫婦になる。ある日、しじらは、母を見ながら女房に言いました。「お前のおかげで、食うには困らなくなったし、安心させる事も出来た。だがな、おらが幼い頃、母はふくよかな人だったのに、今はこんなに痩せてしまった。それがなんだか、辛いんだ。」と。女房は、「南から渡ってきた鳥は故郷を思い、南に巣をかけます。巣から四方へ旅立つとお互い二度とあう事もかなわない事もありますが、親を思う鳥は、生まれた木の枝に百日間、飛んできて羽を休めます。母鳥はそんな我が子を見て喜ぶんですよ。あなたは、ずっとお母様のそばにいたではありませんか。」と話しました。そして、女房が麻・錘・てがいを求めて紡ぎ、機を求めて織りはじめると、見知らぬ者が二人来て、共に織るのを手伝い、布が織れると、女房はしじらに、「明日この布を持って鹿野苑の市で売ってきて下さい。この布はなんの変哲もありませんが、見る人が見ればわかりますよ。」と言いました。しじらは布を持って鹿野苑に行き、しじらが老人に布を見せると、老人は、「近頃、珍しい布じゃ、私に金三千貫で譲ってくれぬか?」と、しじらは老人にその布を譲りました。老人はしじらを自分の屋敷に招き、「これは七徳保寿の酒、飲んでみなさい。」と酒を勧め、老人はしじらに七杯飲ませ、「今飲んだお酒は、一杯飲めば千年の齢を得るもの。あなたは七杯飲み干したから、七千年の寿命を得ております。これより先は衣服を着ずとも寒くなる事無し、ものを食べなくとも飢える事も欲しいと思う事もありません。」と老人が言い終えると、五色の光が差し、老人も、幾重にも続くお屋敷も、跡形無く消え、しじらはいつの間にか自分の家に帰っていました。帰ってきたしじらに女房は、「こんなに長くここにとどまったのは、あなたの親孝行の思いに報いるためです。私は天界より今生と来世の加護をもたらすために遣わされたもの。これより先もお母様と心安くお過ごしください。」と言い、空からは光が差し、花が降り注ぎはじめると、女房の体は浮き上がり天上へと上りはじめました。その後、しじらは母と安楽に暮らし、その生涯を終えました。そして、女房と同じように空に昇って行ったと言う。
この物語はインドから中国を経て日本に伝わった親孝行息子の物語で、「蛤」は、平安貴族からも珍重され、「貝合わせ」などにも利用されて、至極く身近な存在でもあった。この物語は、「鶴の恩返し」と「竹取物語」を合体させたような物語を連想させる構成であるが、親思いの親孝行息子の幸福物語である。
【子敦盛】
平敦盛の妻は夫の死後、源氏の執拗な探索を恐れ、生まれたばかりの若君を一乗寺の下り松に刀を添えて捨ててしまう。若君は、賀茂大明神への参拝の途上の法然上人に拾われて養育されるが、父母恋しさのあまり重い病にかかる。法然上人の説法の折に、聴聞の人々に向かってこのことを語ると、聴衆のなかから敦盛の妻が涙ながらに名乗り出て、母子は再会し若君の病は回復した。そして、父にひと目会いたいと願う若君は、賀茂大明神の夢のお告げにより摂津国の一ノ谷に赴き、ある小さな御堂で父の亡霊と対面する。
「何嘆く 昆陽野生田の 草枕 露と消えにし われな思うそ」
平敦盛(たいらのあつもり)は、平安時代末期の武将で、平清盛の弟である平経盛の末子である。この時点では官職にはついておらず、無官大夫と称された。笛の名手でもあり、祖父平忠盛が鳥羽院より賜った「小枝」(「青葉」の説あり)という笛を譲り受けた。平家一門として十七歳で摂津国の一ノ谷の戦いに参加し、熊谷直実に打ち取られ、熊谷直実が出家する最大の原因となる。
私こと樹冠人の本家筋に当たる家では、この「平敦盛」の伝承を言い伝えている。広島県庄原市には古くから「敦盛さん」という民謡(市の無形民俗文化財)が伝わっていて、敦盛の室の玉織姫(庄原では「姫御さん」と呼ぶ)が、敦盛は生きているとの言い伝えを頼りに各地を巡り歩き、庄原に至って結局そこに住んだという伝承である。平敦盛を討った熊谷直実は安芸国に所領を与えられ、直実は出家したが熊谷氏は戦国時代に至るまで安芸国を拠点に土着しているので、何らかの関係が成立していたと思われる。まだ言えば、「熊谷直実は敦盛を哀れと思い安芸国に若君と玉織姫を呼び寄せて匿い共に生活させた」と思わせる伝説が庄原地区に言い伝えられている。
【二十四孝】
二十四孝(にじゅうしこう)は、元国時代の郭居敬が、孝行が特に優れた人物の二十四人を取り上げ編纂し、中国において後世の範として解説した書物である。儒教の考えを重んじた歴代中国王朝は、孝行を特に重要な徳目とした。この話は日本に伝来し、御所や仏閣等の建築物に人物図などが描かれている。儒教の考えを重んじた江戸時代には、幼少期からこの「二十四孝」を教え込まれ常識化した。
参考までに、この二十四人の名前のみ記載しておく。
「陸績・田眞兄弟・剡子・蔡順・閔子騫・黄香・呉猛・楊香・張孝兄弟・丁蘭・王裒・王祥・姜詩・孟宗・郭巨・董永・舜・劉恒(漢文帝)・黄庭堅・庾黔婁・朱壽昌・曾參・唐夫人・老莱子」
【梵天國】
五条の中納言は、すぐれた笛の技で梵天国王の姫と結ばれることができ、姫を参内させようと天皇が次々に課する難題を姫の計らいで解決するが、「梵天王の判」を要求される難問に対して、中納言は梵天国に赴くことになり、かねて姫を奪おうとしていたために捕らえられていた羅刹国の王を、中納言の不注意で逃してしまい、姫をさらわれてしまう。中納言はさらわれた姫を救い出し、危うく羅刹国から逃げ帰ることができた。後には、中納言は九世戸の文殊、姫は成相寺の観音となった。
この物語は、神仏の縁起を説く「本地物」の一種である。「九世戸」とは京都の天橋立一帯の呼称で、「文殊」とは日本三文殊の一つである智恩寺の文殊菩薩を指している。「成相寺」は宮津市に所在し観音霊場西国三十三所第28番札所に指定されている寺院で、「観音」とは聖観世音菩薩を指している。
【のせざる草子】
その頃、丹波国の「背の山」に、年老いた猿がいた。名前を「ましおの権頭」といった。その子どもに「こけ丸」殿とて、世間並みを大きく上回って、知恵才覚があり、芸能についても優れた人がいた。こけ丸殿が扇をもって、舞を一さし舞い終わって引っ込めば、どんな者でも、その舞を見るなり感動のあまり、ぼうっとしてしまって、舞が面白くないということはなかった。そうこうしているうちに、こけ丸殿は、ようやく二十歳になられた。父母は、「どんな家柄のところからでも、嫁をもらってやる」といっておられたが、こけ丸は、父母の話を耳にも聞きいれられず、「わたしには思うところがある。ありふれた身分のものをどうして妻にし得ようか。たいそうな公卿・殿上人の娘でなくては、妻にしたところで、短い束の間の人生に何の面白いことがあろうか」と思っておられた。こけ丸は、世の中の人たちには、「わたしの考えを身の程も知らない望みだ」と思う連中もいるだろう。だが、それこそ愚かなことだ。われらの先祖である猿丸太夫は、誰もが知る有名な歌人だ。「奥山に紅葉踏み分け鳴く鹿の声聞く時ぞ秋はかなしき」と詠まれた和歌は、これを小倉山荘の色紙の和歌に、藤原定家すら入れたではないか。その他、世の代々の歌人の説にも、わたしたちを、「稲負鳥」「ましらの声」などといって、和歌の中に詠みこんでいる、そういう和歌を知らないのだろうか。おそらくは、系図では、われわれ猿は他の誰にも劣るものではない。ありきたりの連中に馴染んだところで、どうせよというのか」と思い、いつもは岩の間から花を見たり、秋は木々の梢に昇って月を眺め、いろいろな木の実を愛し、たいそう心細やかな色好みでいらした。その後、こけ丸が日吉参詣の帰途、北白河の辺で兎の壱岐守の一人姫が琴を弾く美しい姿を見初め、恋の病となる。こけ丸は、猶も日吉に詣で肝胆を砕いて起請し、故郷へ帰りもせず、苔を莚にしてぼんやり夜を明かすところへ、狐の「いなか殿」が巡り合う。
映画の「猿の惑星」を想起する題材でもある「のせざる」の物語である。「こけ丸」の祖先は、京都の小倉山で藤原定家によって選定された「小倉百人一首」にも入選されている猿丸太夫とある。「稲負鳥」は、古今伝授三鳥の一つで、現在では稲刈りの時に飛来してくる実態不明の鳥を指しているが、実は「稲刈りの時に出没する猿」のことであった。「ましらの声」は、「ましら=猿」である。そして、「兎の壱岐守の一人姫」や「狐のいなか殿」まで登場するとイソップ物語をも想起させる物語構成である。
【猫の草子】
慶長七年(1602年)の八月中ごろ、洛中に猫の綱を解き放せとの沙汰が下り、一条の辻にその旨の高札が立てられた。
ひとつ、都中の猫の綱をといて、放し飼いにしなさい。
ひとつ、都にいる猫を売り買いしてはいけない。
これにそむいたものは、罪に問われる。
この高札には猫は喜んだが、鼠は嚙み砕かれるおそれがあるので世間へ出られないと嘆く。京の都に一人の和尚さんがおりました。毎日都の人を集めては、仏法のお話をわかりやすく説いておられました。そのお話はためになると評判で、人ばかりではなく、犬や猫、鳥までも、和尚さんのお話を聞きに縁の下や木の上に、集まったのでした。ある夜、和尚の夢に鼠が現れ、鼠の窮状を訴えるが、鼠が人に憎まれている次第を説き聞かす。そして次の夜には、和尚の夢に虎毛の猫が現れ、虎の子孫という系図を言い立て、「いにしえに私たち猫は、もともと中国に住むものでした。延喜の帝の御代よりご寵愛を賜り、それから後白河の法皇の時代より綱をつけて側に置かれていました。」と、綱を付けられたいきさつを語り、僧から殺生をやめよと諭されるが、猫は鼠を食うことをやめはしないと言い張り、僧は返答に窮した。その後、鼠と猫は軍団を率いて、五条大橋の袂の中州の東西に陣を張り、今にも戦おうとした瞬間、和尚が登場して、「一戦交えるのならそれでもよい、だだの、拙僧の話を聞いてからでも遅くないではないかな?」と説得して、次の話をした。「よいかの、もともと銀殿は若いものが一戦交えようとするのを止めたかったのではなかったかの?虎殿も、無益な殺生はやめようとお仲間と話されたのではなかったかの?」「一条の辻に高札が立ったのは、ネズミさん達が、あまりに人様のうちで悪さばかりをかさねるからで、たまらず猫さんの綱を解き放とうと思いついたのじゃぞ。」「虎殿、ネズミさん達の悪さが過ぎるゆえ、町の人は綱を解いたのじゃ。それを良い事に面白おかしくネズミさんを捕っておれば、いつかネズミさんがいなくなる。そうなった時、町の人は猫さん達をどうすると思うかの?」人間は身勝手な生き物、それは猫もネズミもよく知っていました。お互いを滅ぼそう、などとは考えた事もありませんでした。しかし、どちらも意地と誇りをかけて集まった者同士、なかなか後には引けません。その時、昨晩から降った雨が山から流れ込んできて、川はいつの間にか水かさが増し、ごうごうと音を立てていました。和尚さんは、「これは大変じゃ、早く向こうへ渡らんとみんな溺れてしまうぞ。」「あの立ち木を倒し船替わりに向こう岸へ渡ろう。」和尚さんの言葉に、寅殿と銀殿は立ち木に取り付き、根元をガリガリかじり、爪を立てました。それに続くように他の猫もネズミもいっせいに木をガリガリと削り始めました。木はまたたく間に根元を削られ、川岸に向かって倒れました。寅殿が言いました。「今日の所は和尚さまに免じてネズミさんと一戦まじえるのはやめようと思う。」と、銀殿もいいました。「我々も、せっかく和尚さんに助けていただいた命を、今日、捨てるのは申し訳ない。」と、和尚さんは笑って答えました。「そうじゃの、ケンカをする事もあるが一つの事を一緒にする事も出来る。合戦など人のマネしてやるほどの事でもないわ。」と。それから猫は綱をほどかれたままでしたが、京の町からネズミが消える事はありませんでした。和尚さんが法話を始めると、お寺の縁の下では、猫とネズミが仲良く座っている事もあるそうです。
比較的新しい江戸期の創作で、在京の禅僧の手に成ると考えられている。訴陳状の形式を借りて、僧の法話を聞かせるのが主眼となっている。
【濱出草子】
源頼朝は大仏供養を行って右大将に任ぜられ、兵衛司十人・左衛門司十人の官途を賜った。中に左衛門司を賜った梶原景時は、その位を嫡子源太景季に譲り、大名・小名が集い祝宴が催される。初番・二日目ともに酒肴やらみごとな引出物などを調え、三日目には江の島詣にことよせて、頼朝公の北の方をはじめ大名の北の方も由比ヶ浜に浜出を企て、船の上に舞台を造り、御賀(おんが)の舞、舞楽など三日にわたり舞い奏で、所領を賜った人々はめでたく所知入りをする。
源頼朝が大仏供養の功労で右大将に任じられた時に、家来たち20名の官位が決まり、その内の左衛門司に決まった梶原景時は、石橋山の戦いで源頼朝を救ったことから鎌倉幕府では重用され侍所所司・厩別当となる。頼朝の信任厚く、都の貴族からは「一ノ郎党」「鎌倉ノ本体ノ武士」と称されていた。一方では、源義経と対立し頼朝に讒言して死に追いやった「大悪人」と古来から批判されている。梶原景時は、鎌倉幕府では権勢を誇ったが頼朝の死後には追放され、一族とともに滅ぼされた。
【和泉式部】
和泉式部(いずみしきぶ)は、天元元年(978年)頃の生まれと伝わるが、当時の女性の素性記録が残っていないため没年は不明である。現代では、平安時代中期に活躍した「中古三十六歌仙」「女房三十六歌仙」の一人として有名である。越前守の大江雅致と越中守の平保衡の娘の間に生まれたと伝承され、母が昌子内親王付きの女房であったため、太皇太后宮の昌子内親王付の女童(おんなわらべ)であった可能性がある。和泉守の橘道貞の妻となり和泉国に同伴し、「和泉式部」の名は、夫の任国と父の官名を合わせたものであると思われる。娘の小式部内侍は母譲りの歌才を示したが、母よりも先に他界した。冷泉天皇の第三皇子である為尊親王との熱愛が世に喧伝されるが、身分違いの恋であるとして親から勘当を受け、紫式部からは「和泉式部という人こそ、おもしろう書きかはしける。されど、和泉はけしからぬかたこそあれ」と『紫式部日記』で批判されている。後には、一条天皇の中宮である藤原彰子に女房として出仕し、彰子の父である藤原道長の家司で武勇をもって知られた藤原保昌と再婚し夫の任国の丹後に同伴した。
【一寸法師】
子供のない老夫婦が子供を恵んでくださるよう住吉の神に祈ると、老婆に子供ができた。しかし、産まれた子供は身長が一寸(現代では3cm)しかなく、何年たっても大きくなることはなかった。子供は一寸法師と名づけられた。老夫婦が一寸法師が全く大きくならないので化け物ではないかと気味悪く思っていた。そこで、一寸法師は自分から家を出ることにした。ある日、一寸法師は京へ行きたいと言い、御椀を船に、箸を櫂にし、針を刀の代わりに、麦藁を鞘の代りに持って旅に出た。京で大きな立派な家を見つけ、その宰相殿の家で働かせてもらうことにした。一寸法師は宰相殿の娘に一目惚れし、妻にしたいと思った。しかし小さな体ではそれはかなわないということで一計を案じた。神棚から供えてあった米粒を持ってきて、寝ている娘の口につけ、自分は空の茶袋を持って泣きまねをした。それを見た宰相殿に、自分が貯えていた米を娘が奪ったのだと嘘をつき、宰相殿はそれを信じて娘を殺そうとした。一寸法師はその場をとりなし、娘と共に家を出た。一寸法師と娘が乗った船は風に乗って薄気味悪い島に着いた。そこで鬼に出会い、一寸法師が娘を守ろうとすると、鬼は一寸法師を飲み込んだ。しかし一寸法師は体の小ささを生かして、鬼の目から体の外に出てしまう。それを何度か繰り返しているうちに、鬼はすっかり一寸法師を恐れ、持っていた打出の小槌を置いて去ってしまった。一寸法師は、鬼が落としていった打出の小槌を振って自分の体を大きくし、身長は六尺(現代では182cm)になり、娘と結婚した。一寸法師の噂は世間に広まり、宮中に呼ばれた。帝は大きくなった一寸法師を大変気に入り、中納言まで出世させた。そして、ご飯と、金銀財宝も打ち出して、末代まで栄えたという。
一寸法師が住んでいた津國の「難波里」とは、現在の三津寺から難波付近だと言われている。また、『御伽草子』には「すみなれし難波浦をたちいでて都へいそぐわが心かな」と表現されている。椀に乗って京に向って出発した「難波浦」は、現在の「道頓堀川」だと言い伝えられている。ちなみに、『御伽草子』に掲載されている内容は、現在伝わっている「良い人の一寸法師」とは真逆の性格に表現されていて、巷に流布している「一寸法師」のお話とはかなりかけ離れていることにお気づきだろう。
【さかき】
九州豊前の佐伯という者が、一族の者に所領を横領されて、京都へ上って訴訟を起こしていたが、全く捗らないで、むなしく年月を過ごしたが甲斐もない。このままではいけないと思って、清水の観音にお参りして、十七日間籠って、仏のお告げの御夢想にしたがい、なんとかしようと思い立って、「たけまつ」という童を一人連れてお参りし、深く祈念をしたが、これといった御夢想もなかったのであった。また、在京中に女と契り、帰国後、本妻に知られることとなり、本妻が嫉妬せず、京の女に同情し呼び寄せ、妻の座を譲る。最後には、本妻も京の女も尼となり、二人の女を失った佐伯も出家することになった。
「さかき」は「さいき(佐伯)」のことで、この物語は九州の豊前国の遁世談である。「本妻が嫉妬せず、京の女に同情し呼び寄せ、妻の座を譲る」ところが特異な点である。現在でも京都で大人気の清水寺であるが、『御伽草子』でも頻繁に登場している。
【浦島太郎】
丹後の国に浦島という者がおり、その息子で、浦島太郎という、年の頃は24、5歳の男がいた。太郎は漁師をして両親を養っていたが、ある日、釣りに出かけたところ、亀が釣れたが、「亀は万年と言うのにここで殺してしまうのはかわいそうだ、恩を忘れるなよ。」と伝え逃がしてやった。数日後、一人の女人が舟で浜に漕ぎ寄せて自分は「やんごとなき方」の使いとして太郎を迎えに来た。姫が亀を逃がしてくれた礼をしたい旨を伝え、太郎はその女人と舟に乗り大きな宮殿に迎えられる。ここで姫と三年暮らし、太郎は残してきた両親が心配になり帰りたいと申し出た。姫は自分は実は太郎に助けられた亀であったことを明かし、玉手箱を手渡した。太郎は元住んでいた浜にたどり着くが、村は消え果てていた。ある一軒家に住んでいた老人に浦島太郎の事を尋ねると、浦島太郎は七百年も昔の人で、近くにある古い塚が太郎の両親の墓だと教えられた。太郎が姫と三年暮らしていた間に、世間では七百年もの年月が経っていたのであった。絶望した太郎が玉手箱を開けると、三筋の煙が立ち昇り、太郎はたちまち老人になった。その後、太郎は鶴になり蓬莱山へ向かって飛び去った。同時に乙姫も亀になって蓬莱山へ向かい、太郎と乙姫は再び巡り会って夫婦の神になったという。
日本各地にある龍宮伝説の一つで、「浦島太郎」はその主人公の名前である。『御伽草子』では竜宮城は海中ではなく、島か大陸にあるように書かれているが、丹後国にはそのような地形が豊富に存在しているので、ベストな選択だったと思われる。『御伽草子』には、春の庭・夏の庭・秋の庭・冬の庭の話も展開されているが、まさに、中国宮城か日本の御所を想像させる構成である。現在伝承されているポピュラーな説話は、『御伽草子』の精神性からは大きく違った「不幸感」を形成した形に変化したことは残念である。
【酒顛童子】
酒呑童子は大江山を拠点として、茨木童子をはじめとする多くの鬼を従え、しばしば京都に出現し、貴族の若い姫君を誘拐して側に仕えさせたり、刀で切って生のまま喰ったりしたという。あまりにも悪行を働くので帝の命により摂津源氏の源頼光と嵯峨源氏の渡辺綱を筆頭とする頼光四天王(渡辺綱・坂田公時・碓井貞光・卜部季武)により討伐隊が結成され討伐に向かった。姫君の血の酒や人肉をともに食べ安心させたのち、頼光が神より兜とともにもらった「神便鬼毒酒」という毒酒を酒盛りの最中に酒呑童子に飲ませ、体が動かなくなったところを押さえて、寝首を掻き成敗した。しかし首を切られた後でも頼光の兜に噛み付いていたといわれている。頼光たちは討ち取った首を京へ持ち帰ろうとしたが、老ノ坂で道端の地蔵尊に「不浄なものを京に持ち込むな」と忠告され、それきり首はその場から動かなくなってしまったため、一同はその地に首を埋葬した。
「酒顛童子」は、丹波国の大江山(京都府福知山市大江町)または京都と丹波国の国境の大枝(現在の「老の坂」)に住んでいたとされる鬼の頭領である。酒が好きだったことから、部下たちからこの名で呼ばれた。他の呼び名として、酒呑童子・酒天童子・朱点童子と書かれることもある。この鬼の集団は、まさに盗賊団であるが、彼が本拠とした大江山では龍宮のような御殿に棲み、数多くの鬼達を部下にしていたという。一説では、童子は死に際に今までの罪を悔い、死後は首から上に病気を持つ人々を助けることを望んだため、大明神として祀られたともいう。これが現在でも老ノ坂峠にある首塚大明神で、伝承の通り首から上の病気に霊験あらたかとされている。大江山の山中に埋めたとも伝えられ、大江山にある鬼岳稲荷山神社の由来となっている。
京都府の成相寺には、この「神便鬼毒酒」に用いたとされる酒徳利と杯が所蔵されている。酒呑童子という名が出る最古のものは重要文化財となっている「大江山酒天童子絵巻」(逸翁美術館蔵)で、南北朝時代後期もしくは室町時代初期に造られたとされている。この内容は上記の酒呑童子のイメージとはかなり異なっている。まず綴りが酒「天」童子であり、童子は一種の土着の有力者・鬼神のように描かれていることがうかがえる。また童子は「比叡山を先祖代々の所領としていたが、伝教大師に追い出され大江山にやってきた」とも述べている。酒で動きを封じられ、ある意味だまし討ちをしてきた頼光らに対して童子は「鬼に横道はない」と頼光を激しくののしった。
【横笛草子】
建礼門院の御所に使いとして参上した三条の斎藤滝口時頼は、容顔美麗な横笛という女房を一目見て恋い焦がれ、和歌に託して思いのほどを告げる。たびたび文を取り交わし、契りを結ぶ仲となるが、二人の仲を裂こうとする父に従わず、滝口は勘当を告げられる。親への孝か、契りを違えるかに思い悩んだ末、出家を決意して横笛のもとを去る。それとは知らずにむなしく男を待ちわびていた横笛は、ある日、人のうわさに滝口入道の消息を聞き、一目会おうと嵯峨野の往生院を探し歩く。横笛は、ある日の夕暮れ、嵯峨の地で、時頼の念誦の声を耳にする。時頼に会いたい一心の横笛だが、時頼は「会うは修行の妨げなり」と涙しながら帰したといわれる。横笛は都へ帰る途中、自分の気持ちを伝えたく、近くの石に「山深み
思い入りぬる柴の戸の まことの道に我を導け」と指を斬り、その血で書き記したという。滝口入道は、横笛にこれからも尋ねてこられては修行の妨げとなると、女人禁制の高野山静浄院へ居を移す。それを知った横笛は、悲しみのあまり大堰川に身を沈めたとも、奈良・法華寺へ出家したとも伝えられる。
斎藤滝口時頼は平安時代末期の武士であるが、生没年不詳である。建礼門院の御所に使いとして参上できる武士の記録が皆無であることが不思議であるが、高山樗牛の作品として有名な小説『滝口入道』では「横笛草子」の内容を詳しく説明している。「嵯峨野の往生院」は、現在では「祇王寺」が継承し、「祇王寺」横に細い道があり、その奥地に進むと隠家の趣きが現れ、秋には紅葉の穴場の一つでもある「滝口寺」も存在している。横笛の死を聞いた滝口入道は、ますます仏道修行に励み、高野聖となった。その後、高野山の大圓院第八代住職を務め、元暦元年(1184年)には、紀州の勝浦で平維盛(重盛の子)の入水に立ち会っている。
所蔵者:ウィンベル教育研究所 池田弥三郎(樹冠人)
平成三十年(2018年)二月作成