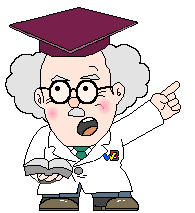【 分数の歴史 】
コーヒータイムしよう! ジュースタイムかな?
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
「分数」は二千年前に誕生した?
「分数の歴史」は、西洋では約千年前のころから分数が使われ始めたようです。分母や分子の名が登場したのは十五世紀の大航海時代といわれています。何かと必要だったんでしょうね!東洋では、中国の『九章算術』(「きゅうしょうさんじゅつ」紀元一世紀ごろ漢の時代?の著作)には分母や分子が登場していますので約二千年前には分数を利用していたと考えられます。当時は、真分数(分子が分母よりも小さい分数)しか考えていなかったようですね。算術の「算」は遠い昔に中国では「竹かんむりに弄」と書きました。「竹を王様が弄(もてあそ)ぶ」ですかね?色んな計算をするのに竹を使っていたようですね。
戸田城聖先生の『推理式 指導算術』の「算術」は、この『九章算術』からの命名と思われます(樹冠人の研究途上での意見)。
日本では、七一八年「算博士」の登場。九七〇年源為憲の著作「口遊」には九九の表が登場しています。江戸時代に入り、佐藤茂春の「算法」とか、関孝和に代表される「和算」(世界的レベルに到達した算術。実は漢文で書かれ、『九章算術』の形式で記述されているのですが。)、藤田貞資の「精要算法」などの芸術が挙げられますが、この当時使用していた「○○例」(○○算にあたる呼び名)などの用語は、現在となっては死語となり消えうせています。「例題」とか「参考例」とかの言葉で生存していますが。