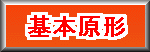 【 売買損益の定義 】 【 売買損益の定義 】 |
「売買損益」の定義を明確にしておきましょう。 「原価」は商人の仕入れ値段で、買値(かいね)ともいう。 「利益・損(損失)」は、「歩合高」である。 「売価」は「原価」と「利益」との和であるか、 「売価」は「原価」と「損」との差で「定価」を意味する。 または、「定価」からいくらかを引いて売った場合の値段 を意味することもある。 これを、「値引き」「割引」という。 【売買損益の定式】 利益・損失・・・原価×歩合 定価・・・・・・原価×(1+歩合)・・・利益の場合 定価・・・・・・原価×(1−歩合)・・・損失の場合 売価・・・・・・定価と同じ場合がある。 売価・・・・・・定価×(1−歩合)・・・割引の場合 ( 指導算術 P.453〜P.455参照 ) |
| 【基本原形1】 定価15000円の家具を1割引きで売りました。いくらで売りましたか。 |
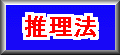 【割引率】 【割引率】【売買損益の定式:定価×(1−歩合)=売価】 15000×(1−0.1)=13500(円) 答 13500円 |
【第一変化問題】 180円で売れば、1割の損がある品物の原価はいくらですか。 |
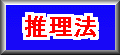 【原価を求める?】 【原価を求める?】【売買損益の定式:原価×(1−歩合)=定価】 □×(1−0.1)=180(円) 180÷0.9=200(円) 答 200円 |
【第二変化問題】 ある品物の原価は2000円です。この原価の2割の利益を見込んで 定価をつけて、これを1割引きで売りました。売価はいくらですか。 |
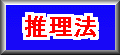 【定価は夢をみた値段?】 【定価は夢をみた値段?】【売買損益の定式:原価×(1+歩合)=定価】 【売買損益の定式:定価×(1−歩合)=売価】 2000×(1+0.2)=2400(円) 2400×(1−0.1)=2160(円) 答 2160円 |
【第三変化問題】 ある商人が仕入れた品物に2割5分の利益を見込んで定価を 5000円とつけた商品があります。もし、原価の1割の利益を 得るには定価から何円引きで売ればよいですか。 |
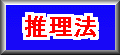 【原価⇒売価⇒定価との差】 【原価⇒売価⇒定価との差】【原価を間違いなく計算すること!】 5000÷(1+0.25)=4000(円) 4000×(1+0.1)=4400(円) 5000−4400=600(円) 答 600円 【別解】原価を1とすれば 1+0.25=1.25・・・定価 1+0.1=1.1・・・売価 1.25−1.1=0.15・・・定価から差し引く額の 原価に対する歩合 0.15÷1.25=0.12・・・原価からの割引歩合 5000×0.12=600(円) |
「定式の覚え方」は暗記するものではないんだよ。「理解記憶」することが大事。 【用語の読み方】利益(りえき)損失(そんしつ)原価(げんか) 定価(ていか)売価(ばいか)割引(わりびき) 【売買損益の定式】 利益・損失・・・原価×歩合 定価・・・・・・原価×(1+歩合)・・・利益の場合 定価・・・・・・原価×(1−歩合)・・・損失の場合 売価・・・・・・定価と同じ場合がある。 売価・・・・・・定価×(1−歩合)・・・割引の場合 ※定式を理解記憶する方法は、虫食い算(充填算)の考え方を 利用することだよ!意味をよく理解することです。 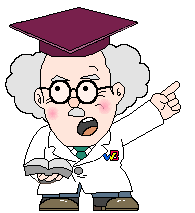 【定式の利用】 【定式の利用】定価÷(1+歩合)=原価 定価÷(1−歩合)=原価 売価÷(1−歩合)=定価 ※第三変化問題の別解の推理法は、大切な推理法です。 しっかり理解しておこう! |