| 問い |
ヒント |
問 題 |
記入欄 |
| 1. |
ウィンベル博士
漢字5字で入力
|
今年は、地理問題が増えると予想されます。
2003年11月、( )院は「地図記号の追加」を発表しました。
この機関は、日本の地図を作っている場所ですね。
中学入試問題の「社会科」は、おおむね9月前後までの「重大
ニュース」を取り上げるのが常識ですが、ひょっとしたらと思い
「地理」の学習にも役立つので勉強しておきましょう!
※( )は機関の名前です。「機関」の意味も理解しよう!
|
答え:
判定:
正解: |
| 2. |
どん兵衛くん
漢字4字で入力
|
今年の話題は何といってもこの人ですよね!

この人は、江戸時代に日本で最初の近代的地図を作った人で、
( )でしたよね。
2001年、アメリカ議会図書館に207枚の複写が発見され、残
りの4枚が2004年に海上保安庁の書庫から発見されました。
これで全ての地図(214枚)がそろい全体図を見ることができま
した。これは、すばらしいことですね。
複写しておくことの大切さも教えられましたね!
|
答え:
判定:
正解: |
| 3. |
ウィンベル博士
漢字4字で入力 |
さすがどん兵衛くんは勉強熱心だね!
去年のウィンベルの時事問題選集でも取り上げましたが、
もう1人わすれてはならない人を紹介しましょう。

この人( )は、北海道とサハリンの地図を作った人で、海峡に
も名前が残っています。
|
答え:
判定:
正解: |
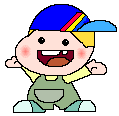 |
ところで、「地図記号の追加」って何でしたっけ?
|
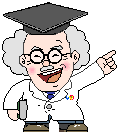 |
ごめんごめん! それは、次の2つだよ。
2万5000分の1の地図の変更がポイントだよ!
|
| 4. |
ウィンベル博士
漢字3字で入力
|
1つ目の記号は、全国にたくさんある施設でしたね。
現代ではこの施設の建設ラッシュですね!

これは、( )の記号でしたね。
参考までに、「地図記号の新設」はここをクリック!
|
答え:
判定:
正解: |
| 5. |
どん兵衛くん
漢字3字で入力
|
そうそう、去年のウィンベル時事問題選集でもやりましたね!
もう1つは、( )の記号でした。
これですよね。⇒
参考までに、「地図記号の新設」はここをクリック!
|
答え:
判定:
正解: |
| 6. |
どん兵衛くん
漢字4字で入力
|
それでは、こんなことも学習しましたよね?
この地図を作っている機関は( )省の特別な機関で、
「測量」「国土情報」などに関して総合的に活動している
んだったよね!
|
答え:
判定:
正解: |
| 7. |
ウィンベル博士
カタカナ4字
で入力
|
実は、ここ数年地図作成に大きな影響を与えている出来事が
あるんだよ!
それは、「市町村の合併」が問題になっているだよ!
だって市町村合併で毎年地図が新しくなるんだもんね?
市名に唯一カタカナを使用している、南( )市は有名だね。
|
答え:
判定:
正解: |
8.
(1) |
どん兵衛くん
漢字2字で入力
|
まだ有名な場所を知っていますよ!
それは、島の名前と市の名前が同じ場所です。
新潟県の佐渡市・( )県の対馬市と壱岐市の3つです。
|
答え:
判定:
正解: |
8.
(2) |
ウィンベル博士
漢字4字で入力
|
政府が市町村合併を推進する目的は、
①地方分権の推進 ②多様化する住民の要求への対応
が挙げられますね。
自分たちの地域を自ら治める( )が見直されているとも
言えますね。
|
答え:
判定:
正解: |
| 9. |
ウィンベル博士
漢字4字で入力
|
やはり地方公共団体にとって地方財政の確立が必要です。
市町村の合併で、財政基盤を強化し、むだを省く行政が求め
られているんですね。
もう少し人口が多ければ( )都市になれる新潟市とか浜松
市の周辺では大規模な合併が予定されています。
このような問題をめぐって、直接住民に問う「住民投票」が各
地で行われています。
そして、地方財政の歳入である「地方交付税交付金」や「国
庫支出金」の配分に大きな影響が出てきています。
これからの地方分権は、「大きくなることは、良いことだ!」と
いう問題ではなく、国に権限が集中するよりも、地方がまとま
って権限を持つという地方分権の考えが主流になり、住民の
大きな関心事となることでしょう。
|
答え:
判定:
正解: |
 |
この人は、現在の千葉県の九十九里町で1745年に生まれ、結婚して佐原村の
酒屋にきました。36歳のとき名主(なぬし)になり、天明の大ききんのときなどは、
難民救済につとめ、佐原村からは餓死者はほとんどいなかったと伝えられています。
そして、なんと50歳になったとき商売を長男にまかせ江戸に出て天文学と測量学を
学びました。そして、20年間も日本各地を歩き続け、1818年に亡くなりましたが弟
子の協力で「大図」「中図」「小図」が、1822年に「日本全図」として完成しました。
正式には「大日本沿海輿地全図」(だいにほんえんかいよちぜんず)と呼びます。
明治時代に作られた近代日本地図のもとになりました。
すばらしい「根気・情熱・努力」の人ですね。 |
 |
この人は、現在の茨城県の伊奈町に生まれ、18歳のとき蝦夷にでかけ、植林や農業
などの指導と地図を作りました。
そして、29歳で江戸幕府の役人となり、樺太(からふと)探検に出発します。
その後、公儀隠密(こうぎおんみつ)として日本各地をめぐり調査を続け64歳で病死し
ました。この人は、北方問題が出題される時によく登場します。
※参考までに、「蝦夷」(えぞ・えみし)は差別用語です。
※古くは現在の東北・北海道を蝦夷地と呼ばれ、いわゆる北方の野蛮人の住む場所
またはその人を指します。ちなみに、南方は「熊襲」(くまそ)です。 |
| おまけ |
国土地理院のHPはこちら!
|