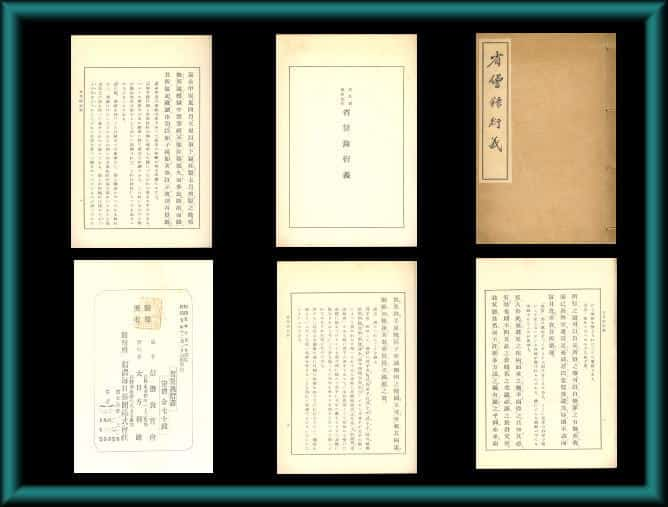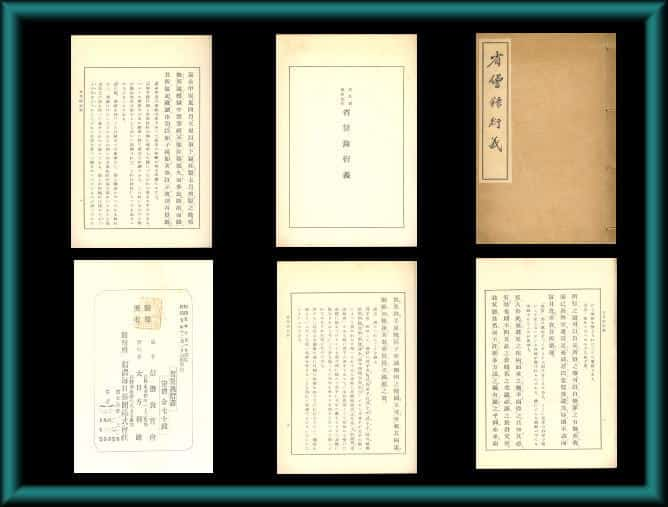『省ケン録衍義』(せいけんろくえんぎ)
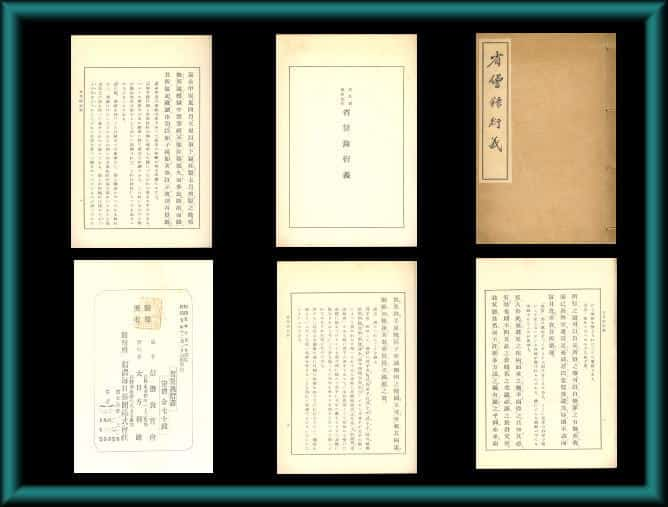


タイトル:省ケン録衍義(せいけんろくえんぎ)
出版書写事項:昭和五年(1930年)十二月一日 発行
形態:一巻全一冊 和装中本(A5版)
編者:信濃教育会
発行者:大日方利雄
発売所:信濃毎日新聞株式会社
目録番号:win-0060009
『省ケン(侃+言)録衍義』の解説
今回紹介する「省ケン(ケンは上部が「侃」で下部が「言」、以下「侃+言」と表記)録衍義」は、江戸幕末の先覚者である佐久間修理こと佐久間象山(文化八年・1811~元治元年・1864)が編纂した「省ケン(侃+言)録」を解説した書籍で、解説本としては岩波文庫本・内閣局本以外で入手できた唯一の書籍でもある。
「省ケン録」とは、「あやまちを反省する記録」との意味であるが、象山が弟子である吉田松陰(文政十三年・1830~安政六年・1859)の密航事件に連座した罪で伝馬町(江戸)の獄中にあったときに、学問・海防・時事などの諸問題を纏めた随想録で、反省文の体裁とはなっていない。明治時代に刊行された書籍には、勝海舟(文政六年・1823~明治三十二年・1899)の序文が掲載され、象山の和歌も附録されて、象山の開国思想の真髄が満載されている。
佐久間象山は、信濃松代藩の下級武士として生まれ、江戸幕末の兵法家・思想家として名高い先覚者である。通称は修理(しゅり)であるが、号を象山、諱(いみな)を啓(ひらき)、字を子明(しめい)と自称した。「象山」の読み方がよく話題になるが、漢学者でもあった象山らしく「後の人、我が名を呼ぶなば正に知るべし」として、「しょうざん」と呼ぶように示唆したとの説もあるが、名前・号についての解説は後段に譲ることにする。「南洲手抄言志録」で紹介した佐藤一斎(安永元年・1772~安政六年・1859)に朱子学・陽明学を学び、山田方谷(文化二年・1805~明治十年・1877)と共に「昌平黌(昌平坂学問所)の二傑」と呼ばれた逸材であった。
また、象山は勝海舟の妹・順を妻としたので海舟とは義兄弟で、海舟も象山先生と呼んだ如く、西洋兵学においては象山は海舟の師匠に当たる。象山は西洋兵学を学ぶため伊豆韮山代官の江川英龍(享和元年・1801~安政二年・1855)に弟子入りし、大砲の鋳造に成功して一躍有名となった。象山が真田藩主に「海防八策」を進言したことは有名であるが、日本初の電信機の発明や地震予知機の開発、そしてガラス製造など斬新的な西洋技術の導入に成功した先覚者であった。門弟には吉田松陰・勝海舟・坂本龍馬・橋本左内・河井継之助・加藤弘之・岡見清熙などの幕末の偉人が多い。しかし、「西洋かぶれ」の汚名を着せられ京都三條木屋町の路上で暗殺されてこの世を去ることとなった。
この書籍には、明治から昭和に活躍した東洋史学者で文学博士の飯島忠夫の「省ケン(侃+言)録に就いて」と題した講義と明治から大正に活躍したアララギ派歌人である島木赤彦の「佐久間象山の和歌」の論評が収録されている。
飯島忠夫によれば、「省ケン録」の題目については、「ケン(侃+言)といふのは『あやまち』で愆と同じく『けん』と読みまして、あやまちを省みるといふことであります。」(中略)「亜米利加の軍艦が浦賀に来て通商を請った時、先生は志士として活動され、それが幕府の政治上の眼から見て、出過ぎた事をしたといふので罪人とされた、その罪を省みられたものでありまして、先生の一生の中最も重大なる時期であり、又先生の精神が強い力で現れているものであります。」と、解説している。
また、「象山」の呼称については、「山の名によってその號を附けられたといふことは、先生御自身の文章『象山記』の中に見えて居り、先生の書簡の中にも書いてありました。」とあり、その山については、「手紙の中に惠明寺は象山惠明寺といふのであって、(中略)寺に山號を附ける時にさう呼んだものであります。」「惠明寺は黄檗宗の寺であって、その開基は木庵といふ人であります。木庵は支那から帰化して来た人でありまして、その弟子が惠明寺を開いたのでありますが開基を自分の師の僧の名前にするのはそのころの習慣であります。」「お寺の言葉は呉音で読むのが普通だったから、象山惠明寺(ぞうざんえみょうじ)といひ、『しょうざんけいめいじ』とは云ひません。先生の號が寺の山號によってつけたとすれば『ぞうざん』であります。併しながら漢学者は漢音、僧侶は呉音で読む、これが徳川時代の一般のならはしであり、そして漢学者は僧侶と区別することを喜んだから、その文字をとって来て『象山』と読んだとする方がいいやうにも思へるのでありまして、どっちでも論が立つのであります。」と、解説している。
そして、啓(ひらき)と子明については、「『啓』といふ名前から『大星子明』といふ名前が出て来るのであって、啓と明とは通じています。(中略)金星のことを啓明と申します。東に出れば啓明と云ひ、西に出れば長庚といふのです。それで『大星』といふのは金星が大きな星であることから導かれ、『子明』といふのは啓明の明るいといふ意をとって来られたのであります。即ち東に大星ありて黎明を知らしめ、やがて大いに世を照して光輝あらしめようとする先生の大抱負があらはれています。つまり、先生の名前によって、先生の大理想を窺ふことが出来るのであります。」とも解説している。なお、「東洋の道徳、西洋の藝(芸)術」との名言はこの「省ケン録」が出典である。
象山の和歌について島木赤彦は、「省ケン録に載っている象山の和歌は百十六首ある。其の中吾人の取り得るは僅かに幾部分に過ぎぬ。取り得るものの少ないが為めに直ちに象山の和歌はつまらぬなど断定するは軽卒である。」「名山大澤は其の規模の大なるだけ夫れ丈けつまらぬ景色も交って居る。つまらぬ景色が交っているから名山大澤の値打がないといふのは馬鹿げていると同じ事である。隅から隅まで気の利いた公園は、全体に纏めて見れば必ず小規模であるに相違ない。(中略)日常生活他人の交際、すべて斯の如しだ。隅から隅まで気の利いた積りでいるうちに、小才子にはまり込んでしまはねば僥倖である。」と、書き出した。そして、象山が七箇月の禁錮中に作った二十二首を選び出して解説した。
獄中聞子規歌
遠知許知爾 奈久寶土騰宜數 妣等那良婆 波播乃美己等耳 許登都天麻思乎
(遠近になくほととぎす人ならば母のみことに言づてましを)
伎乃布気布 阿春登宇都路婦 與能比等乃 許己呂爾仁多流 安治佐為迺破奈
(きのふけふ明日とうつらふ世の人の心ににたる紫陽花のはな)
憂思世事歌
豫能奈可乃 安伎乃之留之加 武散志能也 於保叡乃美等耳 幾里多知和多流
(世の中の秋のしるしか武蔵野や大江の水門に霧たちわたる)
故登之安禮婆 久爾毛留飛等母 夜末多目流 曾保都爾爾太里 宇例波之乃與耶
(事しあれば国守る人も山田もるそほづに似たりうれはしの世や)
七夕歌
比許保志迺 都麻等布己呂耳 那里奴禮杼 伊毛爾阿不倍起 數倍能志良奈久
(彦星のつまどふ頃になりぬれど妹にあふべきすべの知らなく)
多奈波太乃 保思萬都留與波 和岐天末多 布流佐等比等迺 和連遠麻都良武
(たなばたの星まつる夜はわきてまた故郷人のわれをまつらむ)
感情歌
許己呂美爾 伊佐也余婆波牟 夜末比胡乃 古多弊多耳世婆 故惠破怨志麻慈
(こころみにいざや呼ばはん山彦のこたへだにせば聲は惜まじ)
和我於毛比 乎伎乃思多被能 曾與等太耳 伊布比等安良婆 宇禮之可羅末之
(わがおもひ萩の下葉のそよとだにいふ人あらばうれしからまし)
美知乃久能 曾等奈留惠俗能 所登遠許具 布年與里登富久 毛乃遠古蘇於母幣
(みちのくのそとなる蝦夷のそとを榜ぐ舟より遠く物をこそ思へ)
於保宇彌乎 太耶須久和多流 由気布禰乃 破夜久毛幾美耳 阿不余志母加那
(大海をたやすくわたるゆげ船のはやくも君にあふよしもがな)
惠賊志麻也 知之萬乃曾等耳 布禰宇希天 伎美之由流佐婆 遠幾奈都里天武
(ゑぞしまや千島のそとに船うけて君しゆるさば沖魚つりてむ)
破留破留等 左加流伊都志麻 由気布年爾 知加余流伎美乎 彌奴我倭比志散
(はるばるとさかる伊豆島ゆげ船に近よる君を見ぬがわびしさ)
弟子の吉田松陰の米艦を望んで進み行く姿が眼前に見えるようである。・・・・・樹冠人感
布久可勢波 岐美我阿多利爾 可余幣杼母 古等都解也郎武 須倍曾志羅連努
(ふくかぜは君があたりに通へどもことづけやらむすべぞ知られぬ)
弟子の吉田松陰の苦労を思う深い師匠愛を感じる。・・・・・樹冠人感
美知乃彌波 保杼毛破留加耳 遍多太例杼 許故呂波伎美爾 余利仁之毛迺乎
(道のみはほどもはるかにへだたれど心は君によりにしものを)
和多都美乃 志保能夜保幣迺 曾古布可久 於毛比蘇米天之 故登波和須禮受
(わたつみの潮の八百重の底ふかく思ひそめてし事は忘れず)
都禮豆列爾 可岐奈須胡等能 年母古路仁 武可之能非登所 古比之可里気類
(つれづれにかきなす琴のねもごろに昔の人ぞこひしかりける)
雲能破奈乃 宇伎豫等志禮杼 思加理等天 伎美之以麻世婆 曾牟可例那久爾
(うの花のうき世と知れどしかりとて君しいませばそむかれなくに)
佐奈幣等李 宇惠武登志米之 遠也末多乃 可希比乃美豆能 毛里天久夜之伎
(早苗とり植ゑんとしめし小山田のかけ筧の水のもりてくやしき)
伎彌耳古比 安岐乃與比等理 和禮乎例婆 毛能和弭志良爾 幾里幾理數奈久
(君にこひ秋の夜ひとり我居ればものわびしらにきりぎりすなく)
爾遠於毛美 可是耳麻加須流 宇伎布禰波 伊豆例迺有良仁 與羅武登春良牟
(荷をおもみ風にまかするうき船はいづれの浦によらんとすらむ)
以等世馬氐 和弭之起登伎波 余之能夜末 倭気天伊利希牟 比登乃美於毛保由
(いとせめてわびしき時は吉野山わけて入りけむ人の身おもほゆ)
伊等波之伎 余等波志例杼母 由久須衛乃 志良禮奴加羅爾 許己呂比可連都
(いとはしき世とは知れども行すゑの知られぬからに心はかれつ)
私こと樹冠人がこの二十二首を読んだ時の感想としては、歌の基調は萬葉集の譬喩歌を連想する文字使いをしていると強く感じた。そして、弟子である吉田松陰の行動が原因で禁錮の身となり、弟子を思う象山の師匠愛を強く感じた思い出がある。
【参考】 島木赤彦(明治九年・1876~大正十五年・1926)について
柿乃村人の別号を持つ久保田俊彦こと島木赤彦は、明治から大正に活躍したアララギ派の歌人である。赤彦は、教職を勤めながら短歌を作り、正岡子規(慶應三年・1867~明治三十五年・1902)の歌に魅了されて伊藤左千夫(元治元年・1864~大正二年・1913)の門を敲き、左千夫の死後は短歌雑誌「アララギ」の発行人となる。赤彦の歌風は写生短歌と呼ばれ、独特の歌風を確立してアララギ派の基盤を構築した。
所蔵者:ウィンベル教育研究所 池田弥三郎(樹冠人)
平成二十四年(2012年)一月作成