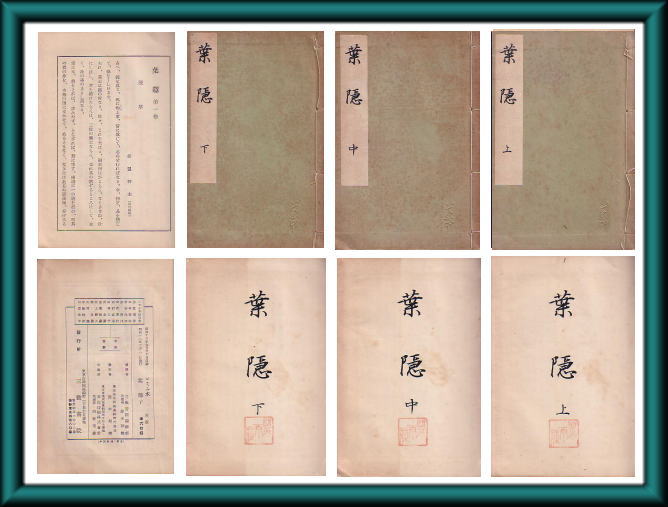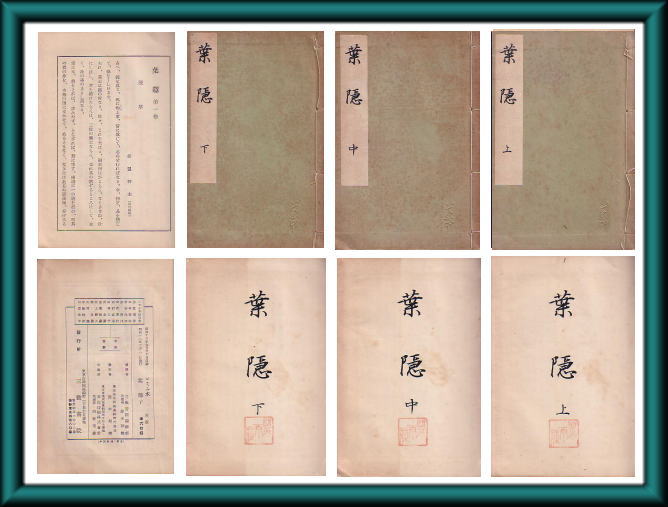『葉隠』(はがくれ)
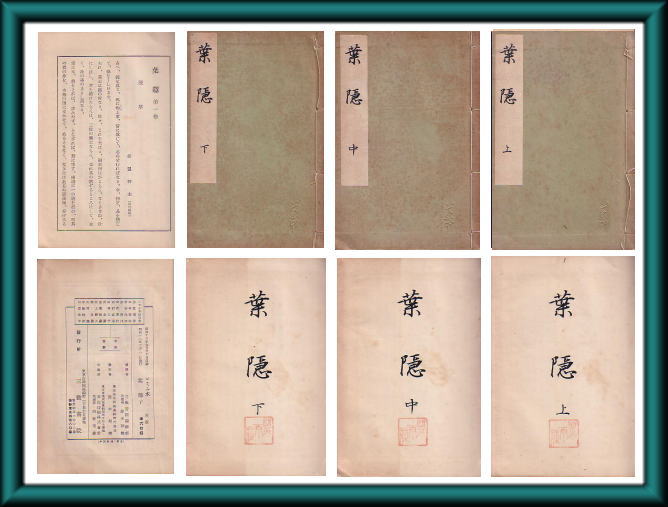


タイトル:『葉隠』(はがくれ)
編輯者:山本常朝
出版書写事項:昭和十二年十月一日(1937年)発行
形態:十一巻全三冊(いてふ本B6版)
編輯者:三教書院編輯部
発行者:鈴木初雄
印刷所:文化印刷株式會社
代表者 西野末雄
発行所:三教書院
目録番号:win-0090009
『葉隠』の解説
『葉隠』(はがくれ)は、肥前国佐賀鍋島藩士の山本常朝(やまもとじょうちょう・万治二年・1659~享保四年・1719)が武士としての心得を口述し、それを同藩士の田代陣基(たしろつらもと・延宝六年・1678~寛延元年・1748)が筆録しまとめた書籍で、『葉可久礼』とも『葉隠聞書』とも呼ばれ、全十一巻に筆録編集した『葉隠』の冒頭には、「この始終十一巻を追て火中すべし」とされ、この『葉隠』は秘本とされていたが、佐賀藩士の間で筆写されて愛読されていた。
『葉隠』とは一体何であるかと聞かれたときに、常朝は「一口に言い切ることは難しいが『葉隠四誓願』は葉隠の要約されたものを表現している」と答えたとある。『葉隠』とは『山里の木の葉がくれに聞き、ひそかに書きとめたもの』という気持ちをこめ、さらには、『陰の奉公』の意味合いも持たせたものではないかと思われる。また、陣基が常朝を訪ねたこの地方には「葉がくし」という柿が多くあるところから、この柿の葉隠れに語ったという説もある。
第一巻の冒頭には筆録者の田代陣基の号である松盟軒主とあり「漫草」の序から始まり、「浮世から何里あらうか山桜」常朝、「白雲やただ今花に尋ね合ひ」陣基の二句が掲載されている。
『葉隠』の中身は「夜陰の閑談」から始まり、次に直茂と勝茂の言行が第三巻から第五巻までの大部分を占め、第六巻から第十一巻までは藩士の言行を主として取り上げている。葉隠の根本精神は総論に述べている「四誓願」(後述する)であるが、これは石田一鼎の「武士道要鑑抄」の三誓願にならったものと考えられ、この三誓願に慈悲の心を加えて一つに纏め上げたものである。この慈悲の心は恩師湛然和尚の教えによるもので、武士は勇気だけでなく、慈悲の心が必要であると説かれていたためと思われる。
山本常朝は、佐賀鍋島藩士で通称は山本神右衛門、元々は「つねとも」であったが出家以後「じょうちょう」と称した。佐賀藩士の山本神右衛門重澄の次男として生まれ、母は前田作左衛門女である。常朝が自らの生い立ちのことを語っている項が「聞書第二」にある通り、「自分は父が七十歳の時の子で生来からひ弱で二十歳まで生きられまいと言われたが、名付親の多久図書の父の血を受け末々御用に立つという取りなしで、初名を松亀と名付けられ九歳の時に佐賀二代藩主の鍋島光茂の小僧として召し出された」という。
常朝は佐賀郡松瀬の華蔵庵において湛然和尚に仏道を学び仏法の血脈を申し請けているので、『葉隠』で慈悲心を非常に重んじている素地はこのとき訓育されたと思われる。そして、神・儒・仏の学を究めて藩随一の学者といわれながら下田松梅村(現在の佐賀県大和町)に閑居する石田一鼎を度々訪れて薫陶を受けた。このことも後の『葉隠』の内容に大きな影響を与えている。
湛然梁重和尚の生年は不明であるが、肥前の生まれで三河国の寺にいたが、同国の長円寺住持であった武雄出身の名僧月舟の推挙により、鍋島家菩提寺高伝寺第十一代住持となった。しかし、寺を去り知友である深江信渓のいる大和町松瀬の通天庵に入った。常朝の父重澄が深く湛然を敬い、生前に法号を授かるほどであったので、常朝も青年時代に足しげく華蔵庵を訪れて教えを受け師事している。
先ほどの冒頭「夜陰の閑談」のなかで一鼎の「要鑑抄」と趣旨を同じくする三誓願の次に「大慈悲を起し人の為になるべき事」の一行を加えているのは、明らかに湛然の影響の表われと思われる。
特に「聞書第六」に、「湛然和尚平生の示しに」で始まるいわば湛然の思想の根幹を示したと思われる項目がある。「出家は慈悲を表にして、内には飽くまで勇気を貯えざれば、佛道を成就すること成らざるものなり、武士は勇気を表にして内心には腹の破るるほど大慈悲を持たざれば、家業立たざるものなり。これに依って、出家は武士に伴ないて勇気を求め、武士は出家に便りて慈悲心を求めるものなり。又慈悲というものは、運を育つる母の様なものなり。無慈悲にして勇気ばかりの士、断絶の例、古今に顕然なり」とあることが特徴でもある。
石田一鼎(いしだいってい・寛永六年・1629~元禄六年・1694)は、幼名を兵三郎と称し、幼年より学を好んで母から制止される程で、十五・六歳の頃には、儒・仏の書物で閲読しないものはない位であったという程の猛勉強家であった。十七歳のとき父を喪い家督を継いで二百五十石を拝領し、藩主勝茂の近侍となり元服後には安住衛門宣之と称した。その後、勝茂の遺命により一鼎より三歳下の光茂の御側相談役となり、佐賀藩第一の碩学として儒学者の力量を発揮してよく補佐した。
ところが、三十四歳のとき、光茂の勘気に触れたのか支藩小城藩に預けられ、その領地の松浦郡山代郷(現在の伊万里市)に左遷された。その理由は明らかでないが、主君の前で私利に走る重臣を面責するなど剛直な性格で、特に殉死禁止の件では、左遷がこの翌年のことから、主君と厳しく意見を異にしたためではないかと見られる。幽居すること八年、寛文九年(1669年)に許されて帰り、佐賀郡下田(大和町)に移り住み、落髪し一鼎または下田処士などと号し、元禄六年(1693年)に六十五歳で没した。
葉隠の「聞書第一」にも 「一鼎申され候は、よき事をするとは何ぞというに、一口にいえば苦痛さこらうる事なり。苦をこらえぬは皆悪しき事なり。」とある。一鼎を尋ねて学ぶ者は多く、三十歳年少の山本常朝も、しばしば門を叩いて教えを請うた。著書の「要鑑抄」は、忠孝を本とし、神儒仏三道の合一を説き、武士道の解明に努めたもので、このなかの「三誓願」を見ても、一鼎の思想が常朝に与えた影響は大きく、葉隠の内容に深くかかわっていることは明らかである。
常朝は京都役を命ぜられ、和歌のたしなみ深い藩主光茂の宿望であった三条西実教よりの古今伝授を得ることのために、取り次ぎの仕事で京都と佐賀を奔走した。古今伝授の全てを授かることは容易ではなかったが、これを受けることができ、隠居後重病の床にある光茂の枕頭に届けて喜ばせ面目を保った。
藩主の光茂が死去するや、側近として仕えた常朝は追腹禁止により殉死もならず、願い出て出家し藩主の菩提寺である曹洞宗高伝寺の了意和尚より受戒し旭山常朝と改めた。佐賀城下の来迎寺村(現在の佐賀市金立町)の黒土原に「朝陽軒」という草庵を結び隠棲し、田代陣基が常朝を慕い尋ねて来たのはそれから10年後のことで、『葉隠』の語りと筆記がはじまる。
田代陣基は、佐賀鍋島藩士で通称は田代又左衛門である。『葉隠』の筆記者として、口述者の山本常朝、その師であった湛然和尚、石田一鼎と共に「葉隠の四哲」の一人に数えられている。田代小左衛門宗澄の子として生まれ、鍋島藩三代藩主の鍋島綱茂と四代の吉茂の祐筆役として仕えたが御役御免となった。山本常朝の庵を訪れ、同じく失意の中にあった常朝と語らい合う内に常朝の言葉の口述筆記を始め、七年後に『葉隠』として完成させ、五代藩主宗茂の時代に再び祐筆役に返り咲く。
【葉隠の四哲】
『葉隠聞書』とも呼ばれた『葉隠』には重要人物が四人係わっているが、常朝は湛然和尚、石田一鼎から教えを受けており、この湛然・一鼎と口述者の常朝と筆録者の陣基を「葉隠の四哲」と呼んでいる。この葉隠では武士道を説いたところがよく知られているが、その中心的な考え方は「四誓願」の四柱に代表されている。
【四誓願】
一、武士道においておくれ取り申すまじき事
一、主君の御用に立つべき事
一、親に孝行仕るべき事
一、大慈悲を起し、人の為になるべき事
「聞書第十一」に「すべての人の為になるは我が仕事と知られざる様に、主君へは陰の奉公が真なり~陰徳を心がけ陽報を存ずまじきなり」とあるように、陰の奉公隠徳を重んじ、いやしくも自分の功績を現わすことを競うようなことがあってはならないという意味で葉隠という書名を付けたともいわれている。
「武士道と云ふは死ぬ事と見付けたり」の文言は有名であるが、文中では、鍋島藩祖である鍋島直茂を武士の理想像として提示しているとされている。また、「隆信様、日峯直茂様」など、随所に龍造寺氏と鍋島氏を併記しており、鍋島氏が龍造寺氏の正統な後継者であることを強調している。
当時、主流であった『聖教要録』で紹介した山鹿素行が提唱していた儒学的武士道を「上方風のつけあがりたる武士道」と批判しており、忠義は山鹿の説くように「これは忠である」と分析できるようなものではなく、行動の中に忠義が含まれているべきで、行動しているときには「死ぐるい」であるべきだと説いている。
当時の武士道に関する一大事件は赤穂事件であるが、主君の浅野長矩の切腹後、すぐに仇討ちしなかったことと、浪士達が吉良義央を討ったあと、すぐに切腹しなかったことを落ち度と批判している。常朝は「上方衆は知恵はあるため、人から褒められるやり方は上手だけど、長崎喧嘩のように無分別に相手に突っかかることはできないのである」と批判している。
「鍋島論語」とも呼ばれた『葉隠』については、幕末になると、佐賀藩の朱子学者であった古賀穀堂(こがこくどう・安永六年・1778~天保七年・1836)などは、佐賀藩士の学問の不熱心ぶりを「葉隠一巻にて今日のこと随分事たるよう」と批判し、同じく佐賀藩出身の大隈重信(おおくましげのぶ・天保九年・1838~大正十一年・1922)も古い世を代表する考え方だと批判している。
実は、江戸幕末時代から明治時代には批判された『葉隠』であるが、昭和の時代に入り、特に今回紹介した「三教書院」が出版された昭和十二年ごろから、軍国主義の精神的支柱教育に活用され、特に「特攻隊」に象徴されるように、「死の賛美」思想は都合がよかったようである。
そして、将来的に、この『葉隠』は活用利用されないように、注視しなければならない書籍の一つである。
【参考】「いてふ本」
いちょうの模様があるので「いてふ本」と呼ばれ、袖珍文庫は明治四十三年(年)に三教書院から発行された文庫本で、明治末から大正にかけて講談文庫など多数の文庫本が出版されたが、その文庫本ブームのきっかけとなった文庫である。出版業績では江戸時代を中心とした近世文学を主にしていることが特徴で、色は藍・茶・緑など多種類あり、ほとんどはいちょうの柄は型押しのみで、希に金を押したものが存在する。三教書院は昭和の始め頃に復興したらしく、四六版の
「いてふ本」という和本を出版している。今回紹介した『葉隠』も昭和期に発行された「いてふ本」である。
所蔵者:ウィンベル教育研究所 池田弥三郎(樹冠人)
令和二年(2020年)五月作成