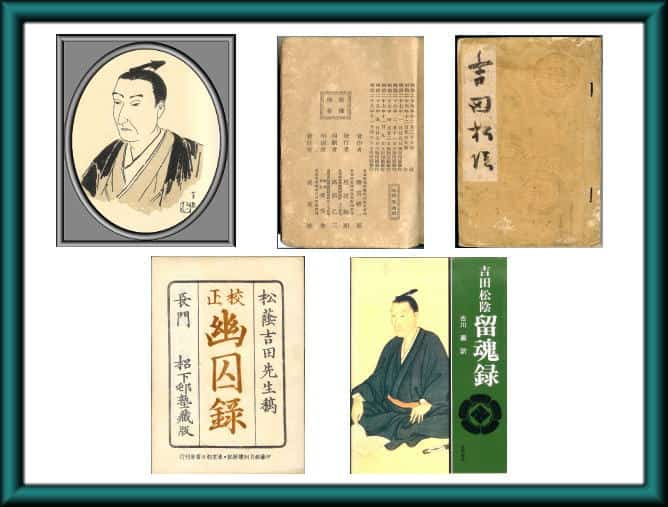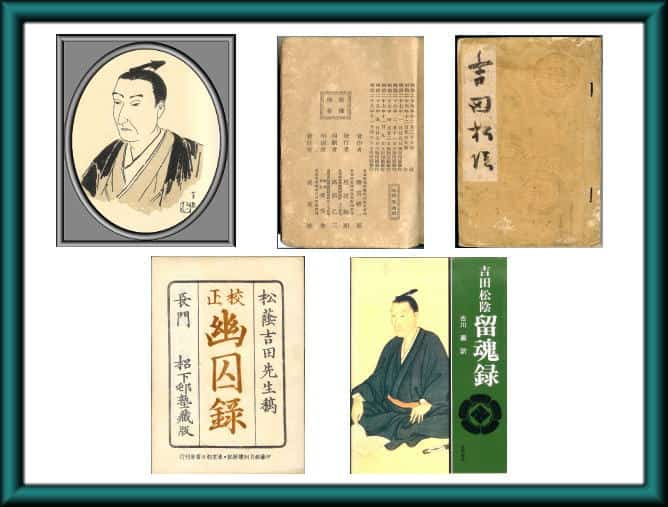『吉田松陰 留魂録』(りゅうこんろく)
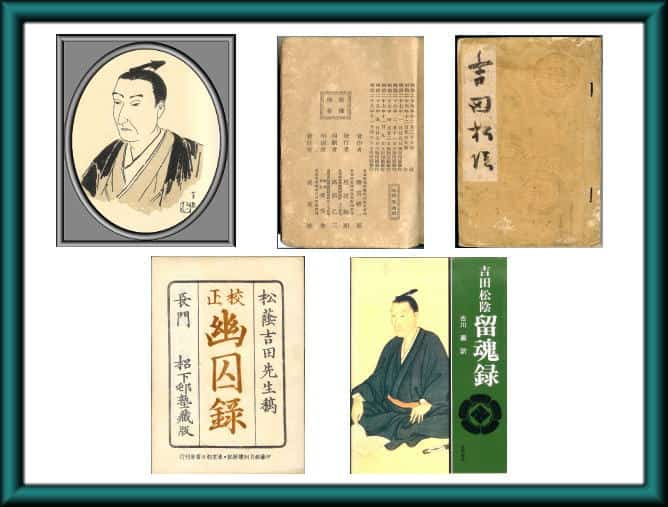


タイトル:吉田松陰 留魂録(りゅうこんろく)
著者:松陰二十一回猛士(吉田松陰)
訳者:古川薫(1925年~)
出版書写事項:平成三年十月三十一日 初版発行
形態:一巻全一冊(A5版)
発行者:荒井 修
印刷所:株式会社清水印刷所
発行所:株式会社徳間書店
目録番号:win-0020005
『留魂録』の解説
今回の「吉田松陰 留魂録」は、吉田松陰(文政十三年・1830~安政六年・1859)の遺書である「留魂録」を、古川薫氏(1925年~)が現代語訳で紹介した訳本である。「解題」と「留魂録」と「史伝・吉田松陰」の三編で構成され、松陰の著作も含めて詳細に整理されて記述されている。また、訳者が「あとがき」で触れているが如く、「留魂録」は「遺書」とは何かといったことを考えさせられる書籍である。
吉田松陰の留魂録の解説は、「昭和期版」である程度説明したので、重複のないように、訳者の松陰に対する思いも含めて「解題」をまとめることにした。
松陰が留魂録の執筆にかかったのは安政六年(1859年)の十月二十五日で、翌日の夕刻には書き終えている。そして、同文の留魂録を二通作成して、一通は門下生で萩藩医の飯田正伯の手に渡り、高杉晋作・久保清太郎・久坂玄瑞の宛名の通り届けられた。そして、飯田正伯が添えた手紙には、十月二十七日の処刑直後、松陰の遺体を引き取る様子が克明に報告されている。
また、遺品も下げ渡されたが、これは松陰と同じ牢にいた囚人で牢名主の沼崎吉五郎の好意によるところが大きかった。その遺品の中に「留魂録」もふくまれていたのである。「先生同室中の頭に沼崎吉五郎と云ふ人、至って篤志の人物にて之れあり候」と飯田正伯は書いている。
沼崎とは、どのような人だったのだろうか。
彼は、福島藩士能勢久米次郎の家臣で、殺人容疑で伝馬町の牢につながれていた。牢名主になるくらいだから、それなりの貫禄は身につけていたであろう。入牢してきた松陰から孫子・孟子などの講義を受ける素養があったようである。留魂録の一通は門下生に無事渡すことに成功し、控えの一通は大切に肌身はなさず獄中で守り、三宅島に移送されたときも大事に保管したようである。
その後、突然許されて、明治七年(1874年)に東京となった江戸に帰った。そして、神奈川県権令となっていた子爵の野村靖に控えの留魂録を手渡したことは、「昭和期版」で説明した通りである。しかも留魂録とは別にもう一通の遺書である「諸友に語(つ)ぐる書」を預かっていたのである。この「諸友に語(つ)ぐる書」は、百字ばかり書き進めたところで筆を置いている。獄中いつ書かれたものか不明であるが、十月十七日から二十四日の間に書かれたものであろうと訳者は予想している。
そして、訳者の鋭い指摘が続く、
「それにしても、この留魂録の成立を側面から助け、飯田正伯らの手に届くように骨折り、さらに預けられた一通を守り通して原本を伝えた沼崎吉五郎の存在を忘れてはなるまい。野村に渡したあと、彼は飄然と姿を消すのである。野村が彼を引き停めて、何らかの職を与えるくらいはわけもないことだったろう。生き残り政府の高官にのしあがっていく長州人の、弱者に対する惻隠(そくいん・傷む心の切なる形容で、困っているのを見聞きして、かわいそうだと同情すること)の情の薄さを嘆くばかりである。」と述べている。また、「地下の松陰とすれば、明治九年のこのとき、留魂録を萩に送るより、沼崎吉五郎の労をねぎらうことのほうを喜んだのではあるまいか。」とも述べている。
訳者は「解題」の最後の「死刑宣告」の章で、飯田正伯らが萩に送った「埋葬報告書」の文面も紹介している。その文面には、獄中他室の人に言語を通ずることを禁するので、松陰は大音声で辞世詩歌を三回歌ったと書かれていたそうである。そのときの辞世は、留魂録の冒頭の詩と次の五言絶句である。
我今為国死 我今国の為に死す
死不背君親 死して君親に背かず
悠々天地事 悠々天地の事
感賞在明神 感賞明神に在り
そして、訳者は処刑七日前の十月二十日に飯田正伯や尾寺新之丞にあてた手紙を紹介しながら、「死に対する松陰の覚悟と、自分の死後に関する行きとどいた配慮は、通常の人間をはるかに越えた見事なものだったというほかはない。そうした心ばえを背景に、日本人の遺書として、それ自体後世まで輝きを放つ『留魂録』は執筆されたのである。」と締め括っている。
所蔵者:ウィンベル教育研究所 池田弥三郎(樹冠人)
平成二十二年(2010年)十月作成