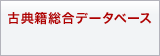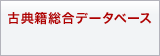『留魂録』(りゅうこんろく)

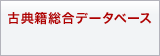
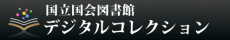
タイトル:留魂録(りゅうこんろく)
著者:二十一回猛士(吉田松陰)
出版書写事項:昭和二十年十月二十日(1945年) 発行
形態:一巻全一冊 謄写印刷 (変形B6版)
編者:柿村峻
発行者:杉山栄一
印刷者:大日本印刷
配給元:日本出版配給株式会社
発行所:株式会社日本書院
目録番号:win-0020004
『留魂録』の解説
吉田松陰(文政十三年・1830~安政六年・1859)については、「幽囚録」で説明したので省略するが、松陰の「留魂録は、安政六年(1859年)処刑前の十月二十六日に完成した。死を前にした松陰が獄中で松下村塾の門下のために万感をこめて認めた遺書が「留魂録」である。幽囚の身である松陰が門下生に宛てた遺書であるため、確実に届くように直筆の書を二通作成したようである。
その内の一通が飯田正伯の手から長州の松下村塾門下生に渡り、この留魂録は松下村塾門下生の間で廻し読みされ書写されて、志士達の行動力の源泉となった。この正本は行方不明となり現存しないが門下生の写本は現存する。山口県萩市の松陰神社に現存するもう一通の正本は、松陰と同室の囚人で沼崎吉五郎が神奈川県権令となっていた子爵の野村靖を訪れ、別本の存在が判明したものである。
今回紹介する戦後まもなく印刷された書籍には、「本文」「註解」「解説」が表記され、「本文」は松陰神社に伝わる松陰自筆の「留魂録」を謄写したものが掲載されている。この遺書は、薄葉半紙を四つ折りにした十九面に認められた五千字にもおよぶ大作である。人間の死生観を教える気品ある遺言書でもある。この留魂録は全十六章で構成され、以下の辞世で始まる。
「身はたとひ 武蔵の野辺に 朽ぬとも 留置かまし 大和魂 十月念五日 二十一回猛士」
「念五日」とは二十五日である。死を覚悟した松陰が郷里の父兄に最後の別れの手紙として認めた書にある「親思ふ こころにまさる 親ごころ けふの音づれ 何ときくらん」とあわせて、あまりにも有名な辞世の句である。留魂録の冒頭に認めたこの句の「留置かまし 大和魂」という言葉が強烈なため、門下生の行動力の源泉ともなり、また多くのファンを現出させたと思われる。
ここで、「二十一回猛士」についての説明をしておこう。
松陰は安政元年(1854年)に「二十一回猛士説」を著した。死ぬまでに全力で二十一回の行動を起こし、門下生たちに模範を示そうとしたのである。「猛を為すことおよそ三たびなり」とあと十八回残っていると述懐している。「七生説」を考え合わせると、残りの六生で各三回ずつ猛を為せば二十一回達成となる。松陰としては色々な思いがあったであろうが、第一回の今生の猛は達成したので思い残すことは無かったのではないかと思われる。
また、松陰はこの「二十一回」は杉と吉田という漢字を分解して読んだと伝えている。松陰の生家の「杉」は、きへんが「十」と「八」でつくりが「三」で併せて二十一である。継家の「吉田」は、「吉」が「十一」と「口」で「田」が「十」と「口」で併せて二十一回となる。また、「猛」はまさに吉田寅次郎の寅が虎を連想させるように、勢いが激しい様子を表現している。
さて、本文で一番印象深い箇所は、初頭の「貫高」と「屈平」の件(くだり)である。
【原文】
「余去年已来心蹟百変、挙げて数へ難し。就中、趙の貫高を希(こいねが)ひ、楚の屈平を仰ぐ、諸知友の知る所なり。故に子遠が送別の句に「燕趙多士一貫高。荊楚深憂只屈平」と云ふも此の事なり。」
【現代訳】
「私は昨年いらい実にさまざまな思いがうつり変わって、それは数えきれないほどである。なかでもとくに私がかくありたいと願ったのは、趙の貫高であり、また楚の屈平であることは諸君のすでに知るところだ。だから入江杉蔵は私が江戸送りになると知って、『燕や趙にすぐれた士は多いが貫高のような人物は一人しかいなかったし、荊や楚にも深く国を憂う人は屈平だけだった』と送別の詩を贈ってくれたのである。」(古川薫訳より抜粋)
貫高と屈平については「照顔録 附坐獄日録」で説明したので省略するが、この件(くだり)に続けて、孟子の「至誠にして動かざる者は未だ之れ有らざるなり」の一節を挙げている。
この章を含めてすべての章をまとめると、第一章は「辞世の句」と「至誠について」、第二章は「評定所での尋問の様子」、第三章は「尋問に対する答弁で『対策一道』を挙げる」、第四章は「供述書について」、第五章は「大原公のこと、間部要撃策のこと」、第六章は「間部要撃について」、第七章は「死の覚悟について」、第八章は「四季の循環について」、第九章は「水戸の堀江克之助について」、第十章は「大学校創立と尊攘堂について」、第十一章は「小林民部について」、第十二章は「高松藩士長谷川宗右衛門について」、第十三章は「勝野保三郎、有志同志のこと」、第十四章は「越前の橋本左内について」、第十五章は「僧月照、口羽徳祐について」、第十六章は「門下生と松下村塾について」と「五句」となる。
留魂録を書き終えて、次の五句を認めて「留魂録」を締め括った。
かきつけ終わりて後
「心なることの種々(くさぐさ)かき置きぬ 思い残せることなかりけり」
「呼び出しの声まつ外に今の世に 待つべき事のなかりける哉」
「討たれたる吾れをあはれと見ん人は 君を崇めて夷払へよ」
「愚かなる吾れをも友とめづ人は わがとも友とめでよ人々」
「七たびも生きかへりつつ夷をぞ 攘はんこころ吾れ忘れめ哉」
十月二十六日黄昏書 二十一回猛士
最後に、「丙辰幽室文稿」に収められた「七生説」について、解説しておく。
「青葉茂れる桜井の 里のわたりの夕まぐれ 木(こ)の下陰に駒(こま)とめて 世の行く末をつくづくと 忍ぶ鎧の袖の上(え)に 散るは涙かはた露か」
これは、楠木正成と弟の正季との自決前のシーンを詩ったものである。正成が弟の正季に「死んだらなにをするのか」と問いかける。正季は「願わくば七たび人間に生まれ変わって、国賊を滅ぼしたい」と答えた。大楠公は喜んで、「自分の心と同じである」と云ってたがいに刺し違えて死んだのである。私こと樹冠人が二十代に愛唱歌として、活動の中にもよく歌っていた詩でもあり、思い出が鮮明に甦るようである。
頼山陽は、旅行中の湊川の地で、水戸光圀(みとみつくに・寛永五年・1628~元禄十三年・1701)の筆による「嗚呼忠臣楠子之墓」を前にして、大楠公の桜井遺跡が忘却されていることを目の当たりにし、人心の荒廃を読み取った。そこで、『日本外史』の中で大楠公の事跡を説き、「七生報国」に生きようとした大楠公を歴史に復活させたのである。まさしく、尊皇の志に生きた代表人物が大楠公こと楠木正成(くすのきまさしげ・永仁二年・1294~建武三年・1336)だったのである。
松陰も三度も湊川を訪れて、涙が落ちるのをとめることができなかったと「七生説」で述べている。松陰は門下生に、この「七生報国」を「七生説」として「七たびも生きかへりつつ」と説き聞かせ、明日の日本を切り拓かんと討幕に駆ける門下生を鼓舞したのである。それに応えて、門下生は筆写して経典として持ち歩いていたことは有名である。
所蔵者:ウィンベル教育研究所 池田弥三郎(樹冠人)
平成二十二年(2010年)十月作成