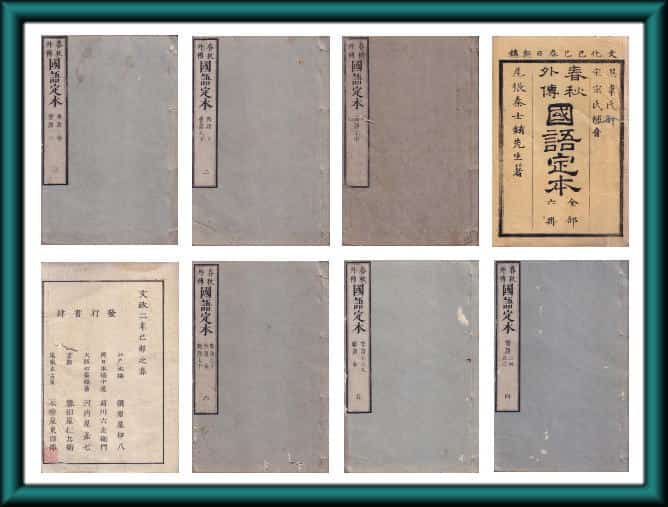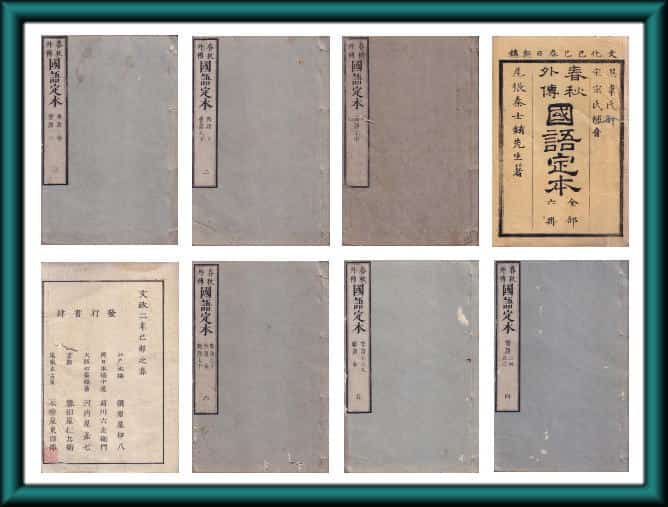『春秋外傳國語定本』(しゅんじゅうがいでんこくごていほん)
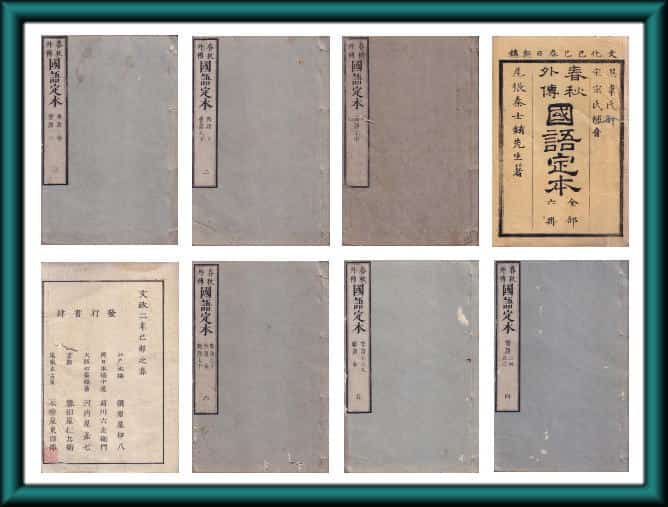


タイトル:春秋外傳國語定本(しゅんじゅうがいでんこくごていほん)
著者:左丘明
出版書写事項:文政二年巳卯(1819年)之春
文化九年壬申(1812年)開板
(早稲田大学蔵書と同等)
形態:二十一巻全六冊 和装大本(B5版)
校読:秦鼎(尾張)
國語解叙:韋昭(呉)
國語補音叙録:宋庠(宋)
附:韋昭略傳 國語定本題言
発行書肆:
江戸 須原屋伊八 前川左兵衛
大阪 河内屋嘉七
京都 譽田屋仁兵衛
尾張 永楽屋東四郎
目録番号:koten-0010007
『春秋外傳國語定本』の解説
「春秋左氏傳」でも解説したが、「春秋」とは「魯春秋」とも呼ばれ、「春秋経」とも呼ばれる。中国の春秋時代の魯国の隠公元年(紀元前722年)から哀公十四年(紀元前481年)までの記録を記した年代記である。孟子(もうし・紀元前372年~289年)が「孔子春秋を作りて、乱臣賊子恐れる」と主張したことから、孔子(こうし・紀元前551年~479年)が「春秋」で大義(人間として守るべき道義・国家又は君主に対する忠誠)を叙述しているとされた。また、「春秋」は孔子が編纂した中国最初の編年体の歴史書ともいわれている。
「外傳」とは、歴史書等に対して補助となる記録・註釈を附した文書を指した。つまり、「春秋外傳國語」は「春秋」の「外傳」で「國語」と呼んだ書籍である。この「春秋外傳國語」も、一説では「魯国の太史」(漢書や論語註に記載あり)とも「孔子の弟子」(論語公冶長篇などから推測された)ともいわれた左丘明(さきゅうめい・生没年不明)が編纂したとされているが、定かではない。
今回紹介する「春秋外傳國語定本」は、「春秋左氏傳」で紹介した尾張の秦士鉉こと秦鼎(はたかなえ・宝暦十一年・1761年~天保二年・1831年)が編纂した藩校の教科書ともなった書籍である。呉国の韋昭(いしょう・?~273年)が解を、宋国の宋庠(そうしょう・996年~1066年)が補音して、それぞれの解叙と叙録が掲載されて、周語(上中下)・魯語(上下)・斉語(全)・晋語(一~九)・鄭語(全)・楚語(上下)・呉語(全)・越語(上下)の構成となっている。また、この書籍は190余年前に発行された貴重な書籍でもある。
この「國語」は、周魯の二ヶ国と春秋五覇国(斉・晋・楚・呉・越)と鄭の八ヶ国の王侯・文官・武官の言動を記録して纏めたもので、当時の会話体が掲載されていることが特徴である。春秋時代を知る重要な歴史書でもあり、孔子が「春秋」では扱わなかった「占術」や「予言」や「権謀謀略」の記録も掲載されて、当時の実話に近い状態の資料として流布した。
今回登場した呉国の韋昭(いしょう・?~273年)が、「國語」の精神を評価して註釈を著した。「古文真寶」でも紹介した唐時代の柳宗元(りゅうそうげん・773年~819年)は、この「國語」の文体を評価はしたが、孔子の精神に反するとして「非國語」を著した。また、この柳宗元の意見に反論したのは、北宋時代の蘇東坡(そとうば)こと蘇軾(そしょく・1036年~1101年)である。
実は、この「國語」は「盲史」と呼ばれる場合がある。それは、「史記評林」で紹介した「史記太史公自序」に、太史公こと司馬遷が「左丘失明して、それにより国語有り」(左丘失明 厥有國語)と記述し、「左丘は盲人になって、それによって(発奮して)国語を著した。」との意味である。現在のところ、この「左丘」と「左丘明」が同一人物であるかどうかは不明である。
なお、伝統的に「春秋左氏傳」と「國語」の編者が同一人物であるとする根拠には以下の点が挙げられる。
①「史記十二諸侯年表序」に、
「魯の君子左丘明が孔子の春秋のために左氏春秋を著した」とあること。
②「論語」に、左丘明の記述(孔子の尊敬する人物として登場)があること。
③「漢書」に、「魯の太史左丘明の作」とあること。
④「史記太史公自序」に、「左丘失明 厥有國語」とあること。
⑤「國語」は「春秋左氏傳」の姉妹編と伝承されていること。
⑥「呉国の韋昭」が、
「左丘明は孔子の『春秋』にしたがって『春秋左氏傳』を著し孔子の大義を
説いたが、それでは不充分なので、さらに周国の滅亡までのことを纏めて
『国語』として著した。その内容は『春秋経』に基づいていないので、
『外傳』と名付けた。」と述べていること。
【参考】 中国哲学書電子化計画
所蔵者:ウィンベル教育研究所 池田弥三郎(樹冠人)
平成二十三年(2011年)七月作成