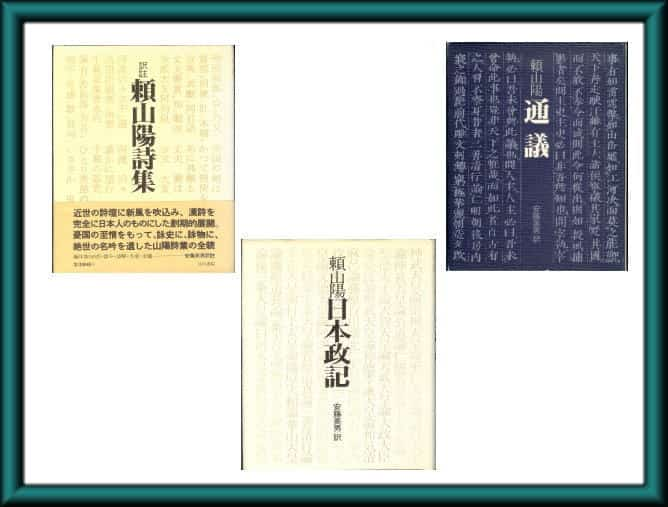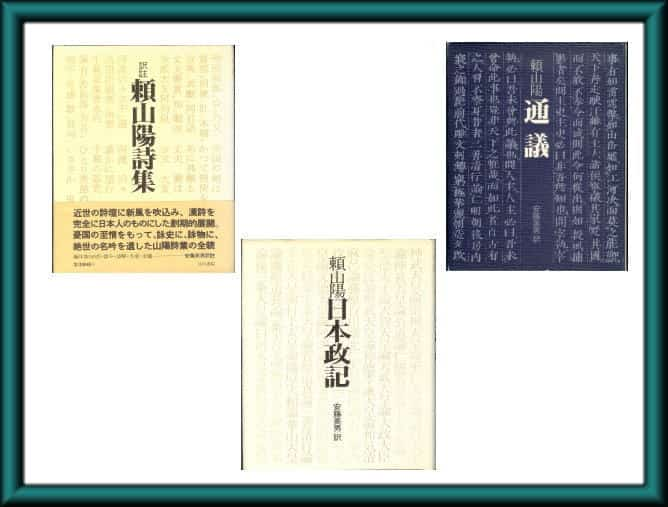『頼山陽 通議』(らいさんようつうぎ)
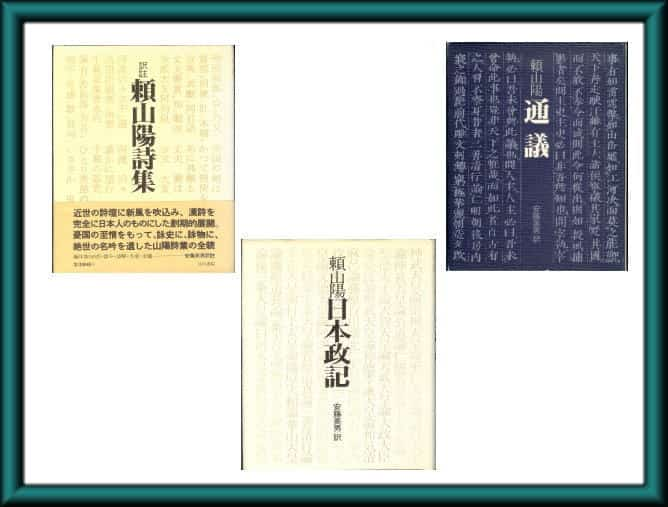


タイトル:頼山陽 通議(らいさんようつうぎ)
著者:安藤英男(1927年~1992年)
出版書写事項:昭和五十二年(1977年)九月 初版発行
形態:一巻全一冊
発行所:白川書院
目録番号:win-0010009
『頼山陽 通議』の解説
今回紹介する「頼山陽 通議」は、頼山陽の代表的著述である「通議」の論文を、安藤英男(昭和二年・1927~平成四年・1992)が現代語訳で紹介したものである。頼山陽の「通議」については、「弘化四年版」である程度説明したので、重複のないように、頼山陽の思いと執筆過程を説明しながら、著者の頼山陽に対する思いも含めて提示することにした。
「通議」(全三巻)は、「日本外史」(全二十二巻)と「日本政記」(全十六巻)とならんで頼山陽の三大著述といわれている。天保十一年(1840年)の初刊版以来、何回も版が重ねられているにもかかわらず、従来の刊本は漢文体のままで、現代語訳版は存在しなかった。そこで、著者が「頼山陽 日本政記」に続いて手がけたのが、「頼山陽 通議」である。
山陽の「通議」に対する思い入れは、半端なものではない。ここでは、「通議」との題名に至る成立過程を見ることにする。
【一】古今総議 寛政八年(1796年)山陽十七歳著
山陽の青年時代の著作であるが、堂々たる長編で名文である。全篇を貫く精神・史識は生涯を通じて持論となった。後年の「隠史」の九議の結論に編入され、「新策」の八議の巻頭に組み込まれ、そして「通議」の論勢の資料となっている。また、「日本外史」の序論の底稿ともなったものである。
【二】隠史五種 文化二年(1805年)山陽二十六歳編
山陽二十六歳の文化二年、仙台の藩儒・大槻平泉が長崎に遊学する途中、広島に立ち寄り、平泉の問いに対して山陽が示した大綱が、「三紀」「五書」「九議」「十三世家」「二十三策」とあり、題が「隠史五種」としてあった。これによれば、「三紀」「九議」が「日本政記」に、「十三世家」と「九議」の一部が「日本外史」に、「五書」「二十三策」が「通議」に変貌していることがわかる。
【三】新書 文化二年(1805年)山陽二十六歳構想
大槻平泉が帰東の途中に備前の武元北林を訪問して山陽の志業を伝えた。北林はその詳細が知りたくて山陽に一書を送り、答書には「八議」「六略」「二十三策」「十八紀事」「六将伝」とあり、題が「新書」としてあった。「八議」「六略」「二十三策」は「新策」を経て「通議」に、「十八紀事」「六将伝」が「日本外史」に編成されている。
【四】新策 文化三年(1806年)山陽二十七歳編
前掲の「新書」の「八議」「六略」「二十三策」を合成して改修したのが「新策」であり、後に「通議」の底稿となる。「新策」として成立した章は「六略」「八議」「二十三論」で、「六略」には「隠史五種」に兵制が加わっており、「新書」の「六略」と同一の項目である。「八議」には総論を加えたものである。また、「二十三論」はわずか二十三日で書き上げたという。
「通議」として甦らせた後は、独立した論稿として世に問う意思はなかったようである。しかし、山陽の没後、杉本貞健がこれを惜しみ、山陽の遺児である支峰・三樹の両人に請うて、安政二年(1855年)に「新策正本」として刊行している。
【五】通議 天保元年(1830年)山陽五十一歳著
「新策」から「通議」に達するまでに二十余年の歳月を経過している。在野の文人として、天下の政治を論ずるとなれば、慎重の上にも慎重を期さなければならなかった。そして、山陽は蘇東坡の「策略」を文章の軌範にしたと伝えられている。蘇東坡の境遇にも共鳴するものがあったのであろう。また、門生で福山藩の藩儒となった江木鰐水(がくすい)が、名文「山陽先生行状」で「新策」と「通議」のことに触れている。
著者は、「頼山陽 通議」の解題の政治哲学の項目で、「思想的に見ても価値があるとともに、今日の政治にとっても、指針とすべきものが少なくない。」と締め括っている。
所蔵者:ウィンベル教育研究所 池田弥三郎(樹冠人)
平成二十二年(2010年)八月作成